ix / Atropa belladonna
紗藍がその後何度か来るよう言ったので、結麻もその都度度会の屋敷へ上がっていた。しかしその全てに翠嵐は同席を拒否した。のらりくらりと適当な理由をつけてかわすのではない、彼の余りに頑(かたく)なな態度に彼女は呆れつつも、その理由は聞かずにいた。
言わないということは、言いたくないということなのだろう。あるいは言わない方がいいと判断したということ。彼は連理を「あまり好きではない」と言ったが、その控えめな言い方の中には逆に強硬な拒絶が見て取れたし、第一探ろうとしてもその時の翠嵐の頭の中と言ったら濃い靄(もや)に閉ざされたようで、結麻には覗くことができなかった。
その日は六度目の打ち合わせで、いつものように日が上りきった頃に始まった。しかしやや曇り気味の空の下、紙の衝立を通った外の光は弱く、紗藍の部屋の中はいつもより薄暗かった。庭木に小鳥が二匹、水の匂いを乗せた風がさわさわと葉を揺らす音に紛れて鳴きあっている。雨が近いとでも話しているのか。
結麻が準備された場所に膝をついて座り、その場の主である紗藍に形ばかりの挨拶をした時には既に、連理と山吹もそこにいた。勿論炎遥は紗藍の後ろに控えている。いないのはいつもどおり、翠嵐だけだ。二度目、三度目の打ち合わせの時こそ紗藍は翠嵐の不在を確認したが、もう今ではそれすらなかった。
このように三人と二匹が揃った所で、紗藍は盆を引き寄せ二人に入れたての茶を出す。結麻はこの部屋を羨ましいとは思わなかったが、そうして出されるものは純粋に羨ましかった。自分の家では水の臭いが鼻につくほど薄くなるまで、もともとあまり味の出ない茶葉を何度も使うのだが、この屋敷はそうではないのだろう。質も量も結麻の家のようなけちけちしたものではないはずだ。
しかし食事にうるさいはずの翠嵐は、そこに文句をつけたことはなかった。
ここにきて質の良いものを口にする機会を持てば、彼は自分の家ではそうではないことに気づいて何か言うようになるのだろうか――それとももう知っていて、それでも何も言わないのか。相変わらず育ちの良さそうな手つきで支度をする紗藍を眺めながら、後者であればいいとぼんやり考えた結麻は、差し出された茶碗の揺れる水面に目を落とした。複雑な組木の天井が波打っていた。
やや肌寒さを感じる部屋にやわらかな湯気を立てるそれを、流儀に則りずずと音をたてて飲み干すと、彼女は空の茶碗を膝の前に置き、それから少し左に寄せた。連理のものは既に空だ。紗藍が最後に茶碗を空けて脇に寄せ、そして顔を上げると少し首を傾げて連理を見た。
いつものように、打ち合わせが始まる。
連理はあの日燃やした見取り図をその後もずっと見せることはなく、それは結麻にとっては行動計画の説明を難しくしているように見えた。しかし何せ、彼女よりずっと経験も能力もある彼が敢えてそうするのだ。余計なことを知っていると小手先の方法で切り抜けようとしてしまい、それは己にも味方にも良い方に進まない。だから主に周囲での警戒を任された結麻にはその知識は入れておかない方がいいのだという彼の言葉に、そんなものかと思いながら彼女は頷いた。
主たる仕事を請け負うのは、この部族で最大の勢力を誇る度会家の現当主、つまり紗藍の役目だ。本来当主は仕事の割り振りを決めたりと事務方のとりまとめをすることが多く、実地に赴くことは滅多にないのだが、実質の権力者たる前当主早稲は、自分の没後家と部族とを背負うことになる娘に箔をつけておきたいと思ったらしい。
連理は形式上は紗藍の支援のため、ただおそらく現実には彼が指示を出し全てを済ますため、紗藍と二人で屋敷に入ることに決まっていた。それは三人の間で何度も確認されたことだから、連理は紗藍にはきちんと見取り図を見せながらの指示や説明をしているのだろう。少なくとも結麻は、そう思っていた。
かつてその場を訪れたことのある連理の説明では、標的となる屋敷は小高い丘の上で、塀を隔てた周囲には竹林が広がっているという。そこに隠れて周りに気を配りつつ、何かあれば中の二人に連絡を入れる。その時は人間よりも身軽な竜、ここでは翠嵐の存在が不可欠になるので、今ここで打ち合わせに参加していないからと言って彼も手を貸さないわけにはいかなかった。もとよりそれが契約の条件だ。
周囲を眺め下ろすような場所に建てられたその屋敷は、丘一つをまるごと敷地にしているような状態で隣の人家との間に相当距離があり、よほど風が強くなければ延焼は考えづらい。最初この話を聞いた時に焼き払うと言った連理の言葉を思い出して呟くように反復した紗藍は、それを聞いて少しほっとした顔を見せたが、連理はそれをたしなめた。
「紗藍様、我々は常に」
「成功を重んずる。一の目的のために最も確実な手段が百の犠牲を伴うなら、その九十九も厭(いとい)いはせぬ……」
「ご存じなら良いのです」
紫色の冷たい視線を伏せた連理は、隣で眉を顰めている結麻をじろりと睨んだ。
「お前もだよ」
「手段を選ばないってことよね」
「だから何だ」
平然と聞き返した連理に肩をすくめると、彼女は前の紗藍に目を戻した。
その日までの打ち合わせの中身をまとめて確認し、ほうと息をついてから紗藍は立ち上がった。
「発つのは明後日。で、いいんだよね? 連理」
「はい」
「そして三日で目的地に着く。その日のうちに仕事を終えて、またここに戻ってくるのは一週間後。そして三人で父上に成功の報告をする」
顔を上げるだけで肯定の返事をした連理の後ろで、山吹がそっと睫毛を伏せた。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
結麻が家に帰り着いた頃には、夕方前だというのに辺りは既に暗く、重たそうな雲がいつもよりずっと速く頭の上を流れて行っていた。もうすぐ降り出すのだろう。
扉に手をかけ、鍵のかかっていないのに肩をすくめた彼女は、中に入ると食卓の上に目をやり、大きなため息をついた。
「ちょっと、何やってんのよ……それ何?」
「何って、カエル。学名は『ヒューラ・ヤポニカ』」
そう言って翠嵐は食卓の上でつついていた、暗がりの中でも鮮やかな緑と分かるカエルの左脚をつまんで高々と掲げ、それに結麻は黙って窓を指差した。
「そんな聞いたことない言葉、いつもどこから仕入れて来るの? いいから逃がしなさい」
「俺が捕まえたんじゃねえよ、勝手に入って来てここに上ったんだ。態度がでかいから名前は『ゆま』に決めた」
「……『帰ってもらいなさい』」
いかにも不本意といった顔で窓を開け、そこから「ゆま」を放り出した翠嵐は、空を見上げて眉をひそめてから雨戸を閉めた。部屋に入る明かりは反対側の窓からのものだけで、しかも外も明るくはない。火の灯されていない室内ではもう手元もおぼつかなかった。強くなってきた風が雨戸をがたがたと鳴らし、結麻は憂鬱そうに天井を見上げた。
「すぐに降り出すわ。かなり激しくなりそう、朝には止めばいいけど」
「あー……雨漏り直しといた」
「ほんと? 助かるわ、ありがと」
素直な感謝の言葉に思うことでもあったのか、僅かに眉を上げた彼はそのまま座らずに台所に向かった。食卓の上に明かりを灯してから、姿を追うように目を移した結麻は感嘆の声を上げて走り寄る。
「私、今日は夕飯の準備もしなくていいのね」
「お前が食う気があるんならな」
「もちろんあるわ。どうしたの? 嬉しい」
薄暗い部屋とは対象的に明るくはしゃぐ結麻から数歩下がり、翠嵐はそこで腕を組んでからため息をついた。数日前、結麻が寝るのを待ってから考えたこと。そして今日までのこと。連理は見取り図をあれから一度も出してこなかった――まるで意地でも見せたくないとでも言うかのように。しかも彼は翠嵐が同席しないことを全く批難しなかった。それどころか来るかどうかの確認さえしなかったのだ。普通に考えれば、その仕事に関わる者は打ち合わせにもいた方がいいに決まっているのに、だ。
結麻がどう思っていようと、彼女が持っている家名は厳然と存在している。そしてそれが部族の内部でどういう意味を持っているかを考えれば、静観していられる結論など翠嵐には導き出せなかった。
だからまず彼は、彼女の機嫌を取ってから話を始めるつもりだった。今の結麻は、内容がどうであれ自分に初仕事が回ってきたことで一種の興奮状態にあり、今回の仕事を断れなどと言った所でまともに話を聞いてもらえる状態ではなさそうだったからだ。
結麻の身に何かあれば自分の命にも関わりかねない。ほかの言葉を塗り隠すように口の中で呟くと、翠嵐は腕を解きながら、髪をふわりとなびかせて振り向いた彼女に口を開いた。
「あのなぁ……」
「そうだ、発つの明後日で決まったの。翠嵐も一緒。打ち合わせは何でもいいけど仕事は断れないわよね? 明日準備するの手伝ってくれるでしょ? 珍しくいい人なんだもの」
まくしたてるように笑顔で言う結麻を前に、人差し指を上げかけた翠嵐はこれは失策だったと思わざるを得なかった。舞い上げてしまっただけだ。彼はがっくりと項垂れ返事をした。
「……分かった」
「良かった。私、今日の翠嵐、大好き」
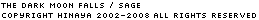 (9)
(9)