x / Gymnaster savatieri
すっきりと晴れた翌朝早く、結麻は定期船に乗って隣の集落に向かった。
結麻の集落を含むこの周辺は、小島が肩を寄せあうようにして浮かんでいる地域で、その島のそれぞれに異なる部族が根を張っている。いくつかは結麻らと同じ稼業を営んでおり、そういう意味では商売敵でもあるのだが、中には彼らを相手にする商店を営む者が集まった島もあって、そこでは客も店主も身の上話を一切口に出さないことが暗黙の了解になっていた。
中心部に並ぶどの建物も、店が一階自宅が二階の多層造りで、平屋ばかりの周囲の島とはひと味違った様相を呈している。その特徴からこの集落は俗に「きだはしもち」とか単に「きだはし」とかと呼ばれていた。階段有り、程度の意味だ。
結麻の集落には、そこに住む人々が自分の庭で作った野菜や釣り上げた魚、屠(ほふ)った鶏などを持ち寄り売りさばく小さな市は開かれているものの、きだはしのような立派なしつらえの商店や、それを結ぶ流通の仕組みなどはない。
とは言っても、いつもは使わないようなものを揃えたければここに来るしかないのは確かだが、ここでしか手に入らない日常生活必需品もなかった。そのため集落の者は誰もそう頻繁にこの島を訪れる必要がなく、連絡船は瀬渡し程度の規模のものが十日に一度出れば十分だった。結麻も、翠嵐と契約を結んだ後ここを訪れるのは、今回が初めてだ。
船に竜を連れたものはいなかった。彼らの中では竜はあくまで主たる己が使役する従、商売道具であり、それを自分の買い物に連れていくなど身軽さが失われるだけで意味がないからだ。大荷物が予想される時、荷物持ちとして同伴させることはあったが。
ただそれとは違う考えを持つ結麻も、その場には翠嵐を連れていなかった。彼は「船酔いする」などと言い訳をしたのだが、それが本当の理由でないことくらい結麻には簡単に分かった。大きくはない船だ。百歩譲って悪意や侮蔑はなかったとしても、他の船客の好奇の目には晒されることになるだろう。「もしその立場なら、自分も嫌だと思ったに違いない」。結麻はそう思い、そのため彼女は彼に、向こうで合流さえすれば構わない旨を伝えたので、どうやら彼は今人の姿も竜の姿もとらず、ただ意識だけが結麻の中で眠っているらしかった。
こうして少しではあるが遠出をする時、翠嵐の姿が見えないのは少し結麻に不安を覚えさせた。それでも揺られる船中、彼女は自分の鳩尾の少し上がいつもより温かいような気がして、そこに触れてはほっとした。
祖父母の没後、翠嵐を呼び出すまで彼女はずっと一人でやってきた。家名のせいで冷たく当たられていることも実感していたが、それをつらいとか不安だとか感じたことなどなかった。だというのに今更。おかしなことだとは思ったが、彼女にはそれが嬉しくすらあった。今の彼女は独りではない。
目立たない船着き場に着岸し、それぞれが目的の場所に向かって散って行く中、結麻はのんびりした足取りで中心街を目指した。時刻を知らせる鐘を打ち鳴らす櫓が見える。昼の鐘がなるのはもう少し後だ。
結麻の集落にいるのと同じ小鳥が、頭上に伸びた梢でちよちよと鳴き合っている。黒い体で頬のあたりだけが白い、かわいい鳥だ。
「いい天気」
そう呟いた彼女は立ち止まり、目一杯の背伸びをするつもりで腕を上に伸ばしたのだが、運悪くそこにちょうど翠嵐が姿を現したので、彼女の拳は危うく彼の顔を直撃するところだった。
「なんでそんな所にいるのよ」
「お前はどうしていつもそう暴力的なんだ」
「急に出て来ておいて失礼ね、いるって知ってたら他所でやるわよ」
どうだか、と肩をすくめた翠嵐は、結麻の頭の後ろに見える町並みに目を細めた。ここらはまだ明るい林の中を通る小径といった風情だが、少し先は大きく開けて、見慣れたものより高い屋根が連なっている。「きだはしもち」の名の由来だ。
翠嵐は結麻を楽に頭一つ分越すくらいの身長があるものの、腕はやけに筋が目立つし、遠目に見てもあまり頼りがいのある体格ではない。心配になるほど細い訳ではなく、よく言えば「要らないものがついていない」体型なのだが、それと並ぶとどうしても結麻には、万人並みであるはずの自分の体が丸みを帯びすぎているようで遠慮を感じざるを得なかった。
連理と並んで歩く時にはそういうことを気にした覚えはなかった。そして連理も十分に細身、というより痩せていたはずだ。何とはなしに自分の手のひらに目を落とし、結麻は頭上で遠くを眺めている翠嵐の顔を見上げた。
確か、彼が来て割にすぐの話だった。対等に扱おうとすること自体が既に対等ではないのだと彼は言った。では今はどうだろう。
「特別」を見出すことは、どうなのだろう――彼女は口の中で呟き、それに翠嵐は気付いたようで肩をすくめてみせた。
「『思ったことは言う』は?」
「何思ったか忘れちゃったわ」
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
二人が中心街に入ると、案の定翠嵐を振り向くものは多かった。
ここに訪れるのは(誰も名乗りはしないものの)同じ稼業の者が多く、紫の瞳を持つ者はそうだと踏んでまず間違いがない。当たり前のことだが、知らない人間が沢山行き交っている。その誰もが一瞬不意をつかれたような顔で翠嵐を見るので、結麻はどこも自分の集落と同じような考え方を持っているのだとぼんやり考えた。
竜を連れているものがいない訳ではないが、その皆が人間を数歩前に、竜を後ろに従える形で歩いている。方々から人が集まるこの場でも、やはり主が竜と――なかんずく人の姿のそれと並んで歩くのは特異なことなのだ。
しかし商売慣れしている商店主はさすがのもので、翠嵐を見てもにこにこと、愛想のいい笑いを全く変えなかった。結麻はそこで必要なものを揃えようとしたが、少し考えてから、同じものを売っている他の店も覗いてみることにした。まだ自ら稼いだことがある訳でもなく、父母、祖父母の遺したもので食いつなぐしかなかった彼女の手持ちは多くはない。
通りを端まで行き着いた頃、正午を知らせる鐘が響き、結麻は櫓の方を振り向いた。
店先をいそいそと動き始める人がちらほら目につく。店員が昼を取りに出るのだろうか、そう思うと途端美味しそうな匂いが鼻先をくすぐり、彼女は思わず後ろを振り返った。すぐ近くに、中で食べられそうな店がある。
でも。結麻は少し考えて、食事は帰ってからにすることにした。さっきの店で全て揃えてしまわなかった理由を、ここで無視する訳にはいかなかった。戻れば食材は、ここで出来合いのものを食べるよりずっと安く手に入るのだし。そう言い聞かせるようにして、結麻はその店に背を向けた。
彼女と同じくらいの年頃の少女が数人連れ立って中に入って行く。皆結麻とは違い、鮮やかな服に身を包み、髪をかわいらしく結い上げて楽しげに言葉を交わしていた。彼女らが店の中に消えてしまうと、結麻は小さなため息をついた。
「行けば?」
「え?」
そこ、と翠嵐は先ほどの店を指差す。次第に人が集まって来ていた。彼は肩をすくめた。
「混むぞ」
渋る結麻に、彼はため息をついた。
「俺は食わなくていいから。好きなの食べてくれば」
それなら大した金額ではないはずだ、彼は言外にそう言っていた。その顔を見上げて首を傾げてから、結麻はにやと笑ってみせた。自分だけなどまっぴらごめんだった。
「私、お腹空いてないの」
「嘘つくなよ」
「空いてないわ」
早く済ませて帰りましょ、と彼女は翠嵐の手首を掴んだ。
近くを歩いていた人がぎょっとしたような顔でその様子を見ていたが、彼女は気にしなかった。人は人だ。自分は自分。そして自分はこれでいい。
通りで最安値をつけていた店を巡る間、彼女はずっとそうして翠嵐の腕を掴んでいた。冷たさを感じる鱗に覆われた竜とは違う、人と同じ、温かなものだった。
すれ違った人の後ろに付き従っていた土色の竜が、それを見て小さな声でケンと鳴いた。
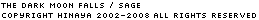 (10)
(10)