viii / Lilium lancifolium
こうだろ、と食卓の天板を指でなぞる翠嵐の顔をまじまじと見つめ、結麻は感嘆の声を漏らした。
「よく覚えてるわね」
「お前はなんで覚えてないんだ」
「普通の人間はあんなちょっと見たくらいじゃ覚えてらんないわよ。それに翠嵐が覚えてるなら私には必要ないじゃない」
「はあ、そうかい」
竜は食事を取らなくても生きていける。
時間に縛られず生き続ける彼らにとって、死は訪れないと言っても過言ではない、遠いものだ。こうして人間と契約を結び、いつもいる世界から現(うつつ)の世に出てくれば、契約中は主と生死を共にする以上それにも一定の限度があることにはなるが、それでも彼らは食べることを必要としなかった。
しかし翠嵐は良く食べた。その上結麻の手料理に文句までつける。なら自分で作ってみせろと結麻が言えば、のっそりと台所に立った彼は、彼女の期待を裏切る鮮やかな包丁さばきを披露し、何故かそこそこの味のものも出してくるのだ。
腕があるなら自分で作ればいいと彼女は散々言うのだが、彼はそれは嫌がった。面倒なくらいなら不味い方がいいというのが言い分だった。そしてまた際限なく文句をつける。
それでも結麻は「食べなければ良いのに」とは言わなかった。そうして彼が逐一つける文句も、ある意味では褒め言葉だと受け取っていた。敢えて良く言えば、おおらかだ。
本当にどうでもいいと思っているものや反感を覚えているものには、翠嵐はきっともっと控えめか、あるいは何も言わないだろう。関わりたくないものにはよそよそしく、できるだけ刺激しないようにする。「竜の姿より便利だから」といつも人の姿でいるにも関わらず、面倒な繋がりの増えることを厭うがために、人のいない所を選んで時間を過ごす彼の生活は、それの一つの発露だ。
そして。興味を持たれず、存在を認識されず、見向きもされないのは何よりつらいこと。そうでないなら、あとの表現の仕方はそれぞれだ――結麻の方もそう思っていた。だから、ぶつぶつ言いながらであってもちゃっかり手をつけ食べ上げるのなら、それは翠嵐に結麻が受け入れられている証拠であり、「関わりたくない」と思われてもいないということだ。これで表現の仕方さえ素直ならと思わない訳でもなかったが、一応喜ばしいことだった。
とにかく翠嵐はその日、結麻が作ったごった煮を(文句を言いつつも)きれいに平らげて、その器をずいと食卓の隅に寄せ、そこにあった小瓶が押し出されて落ちかけたのを信じられない俊敏さで受け止めると、賞賛の拍手を送る結麻の前でその瓶の蓋を開け、中身の調味料を天板の上にぶちまけた。
「ちょっと、何してんのよ」
舞った調味料の粉にむせながら結麻が払うように手を振る。その前でいかにも不本意とばかりに眉間に皺を寄せた翠嵐は、天板の中心あたりを人差し指でつつきながら、言った。
「ないんだよ。書くもんが」
何を書くつもりなのだと尋ねた結麻の前で、彼がぶちまけられた調味料の上をなぞり描いてみせたのが、先ほど度会の屋敷で早稲と紗藍に見せてもらった見取り図だった。
「あんた、いなかったのに」
「お前が見たものは俺にも見える」
「またそんなことしてたの」
結麻は肩を落とし、その鼻先を翠嵐は、非常に心外という顔をして指差した。
「お互い様でしょうが。お前が飽きもせず呼び続けるから、糸垂らしてる間中耳の後ろが痒(かい)いったらもう……勘弁してくれ。一度返事がなきゃ、答える気がないことくらい分かるだろ」
「そんなの『呼ぶな』って一回言えば済むことでしょ。何も言わないから悪いのよ、てっきり聞こえてないのかと。第一無視するなんて感じが悪いわ。炎遥や山吹みたいに言うことを聞けとは言わないけど、その点については一言詫びを入れなさいよね。私に」
「そりゃあ申し訳のうござんしたね」
参りましたとばかりに肩をすくめてため息をつき、そんで、と彼はもう一度天板に指をつくと、とんとんとそこを叩いた。
「これが見取り図」
「うん」
「でも、これは意味がなかった――いや、『重要じゃなかった』。あるいは」
「あるいは?」
それには答えず、ただ「だから消す」と翠嵐は天板の上を手で払い、書かれた図は無惨に散り去った。散らかった足元をげんなりした顔で見下ろした結麻は、そこに落ちていた調味料の中から、まだ形が残っている小さな実をつまみ上げると、それを天板に置いて頬杖をついた。
「重要じゃないってどういうことよ? 侵入するなら位置関係は大事じゃない」
「だけど燃やしたんだろ。あの……何つったっけ、今日の頭の黒い男」
「連理」
そう、と頭を掻いた翠嵐は、結麻の前に転がっていた実をつまみ上げ、それを灯りにかざしてから元の位置に戻した。
「麻(あさ)?」
頷いた結麻は先を促した。
「連理は覚えているから燃やしたんじゃない? 前行ったって言ってたもの。それか早稲さんが持っているから、紗藍のは要らないって思った」
「いや」
『だとしても、敢えて燃やす必要がない』。翠嵐が口に出す前に、結麻はその言葉を聞き取った。しかし、だから何だと言いたいのかが彼女にはさっぱり分からなかった。重い空気が降りて来たので、居心地の悪さを感じた彼女は手元の麻の実に目を落とし、中指で弾くとそれは翠嵐の額に当たって床に落ちた。
「つまり何よ?」
眉を顰めて問い質そうとする結麻に、彼は腕を組んで険しい顔をするだけで返事はなかった。考えていることも、一つを除いては読めない。
「翠嵐、連理が嫌いでしょ?」
「まあ……好きじゃないね」
敢えて控えめに言い直した彼に結麻は肩をすくめ、あ、そ、と呟くと食卓に手をついて立ち上がった。
「もう寝るわ。緊張したから、疲れた」
「どうぞ。そしたら俺は心置きなく物思いに耽(ふけ)れる」
何を物思うつもりなのよと苦笑まじりに言いながら衝立の向こうに消えた彼女に、頬杖をついたまま手を振った翠嵐は、床に落ちた麻の実を拾い上げ、手の上で転がした。
その昔、誰の手によるのかは知らないが、花にはそれぞれ言葉が決められたという。麻の言葉は「運命」だ。彼に言わせれば、世の中で五番目くらいに「笑える」単語。
しかし。
家。そこまで考えて翠嵐は目を閉じた。結麻はまだ微睡(まどろ)んでいるだけで、眠ってはいない。
「……面倒臭えな」
彼は椅子をずらし、食卓に頬をつけてため息を落とした。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
そのことについて、紗藍は何も知らされていないのだという。では、あくまで。連理は確認するように早稲を見、また早稲もそうだとばかりに頷いた。
連理があの場で見取り図を燃やしてしまったのは、万が一結麻がそれを覚えてしまってはまずいという配慮からだった。早稲が先に二人に見せた時間、そして紗藍が同じものを見せた時間。見取り図に描かれていたのは広く、部屋数の多い屋敷だ。そう簡単に覚えられるものではないにしろ、もしもという可能性もある。
あそこに結麻の契約竜がいなくてよかった、と連理は思った。主の行く先々に付き従わず、その上呼んでも来ない契約竜。彼は翠嵐と言葉を交わしたこと、それどころかまともに見たことさえなかったが、それでも結麻と翠嵐との間はこの集落で当たり前とされているものよりずっと壊れやすい関係なのだろうと判断した。
「あの竜は結麻を、便利な依り代(よりしろ)程度にしか考えていないに違いない」。そう考えた連理の頭の底には、集落の誰もと同じ、竜とは従うものという固定観念がある。父にも、その父にも。そして自分にも、山吹は常に「従」だった。確固たる、一番安定した枠だ。そこから外れた主と竜との間が平安であることなど考えられない。なぜならそれは、歴史が培った戒めでもあったから。
だから結麻は契約こそできたとは言え、翠嵐にいいように利用されているだけだ。それが連理の出した結論だった。
呼び出した時の周りの状況を考えてみれば、彼女が簡単に屈服させられるような相手ではない。この集落の常識に照らすなら、あの経験の浅い結麻に翠嵐が愛想を尽かして契約を切っていないのは、彼らの間では、ここでの一般的な主従が逆転しているからに決まっている。それならば彼らの連携は弱く、脆く。少なくとも山吹が心配するようなことにはならないはずだ。
重い門扉が閉まるのを確認してからすっかり暗くなった辺りを見回し、尾の先に小さな火を灯した山吹を先に行かせて、連理は両親の待つ家路についた。
ちょうど結麻の家で翠嵐が、結麻が寝てしまうのを待ちながら、食卓の上の麻の実から芽が出ないものかと考えていた頃だ。
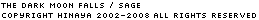 (8)
(8)