vii / Deutzia crenata
「……えと」
二人を前に座った紗藍は、困った顔をして横に目をやった。
早稲がいた部屋と同じく板張りの、しかしそう広くはない部屋だ。二方が大きく庭に面し、明るい日差しが紙の衝立ごしに屋内を照らしている。自分の部屋――とは言ってもそれが「家」のほぼ全てなのだが――とは大した違いだと結麻は思った。ただ、そこに不満がある訳でもない彼女は羨ましく思うこともなかった。
紗藍の後ろには今、炎遥が控えている。今日彼はずっと人の姿のままだ。そしていつ呼ばれたのか、その部屋に入った時にはもう一人男がいた。座った連理の後ろについた彼が山吹であることに気付くまで、結麻には少し時間が必要だった。
薄い栗色の髪をひとつにまとめて垂らしてある。結麻は山吹が人の姿でいるところを見るのはこれが初めてだったが、彼女の想像の中では彼は「彼」ではなく、どちらかといえば「彼女」だった。だから彼女は少し申し訳なさそうな顔で肩をすくめ、それに山吹は悪戯っぽい笑みを返した。それがまた結麻には意外だった。こんな表情をするとは思ってもいなかった。
「結麻のところの」
紗藍がすまなそうな顔をするので、結麻は、ああごめんと苦笑した。
「『翠嵐』。うちのの名前」
「そっか。彼にも聞いて欲しいんだけど……」
いました、と紗藍に耳打ちをした炎遥は、すぐに彼女の後ろに退いた。放った虫が翠嵐を見つけたらしかった。紗藍が尋ねるような目で結麻を見、それに結麻はため息をついて手を広げた。
「あいつなら今、崖の上から釣り糸垂らしてるわ。さっきから来いって呼んでるんだけど、動きそうにないわね」
「釣りをするの? 竜が?」
おかしそうに笑ったのは紗藍だけだ。連理は「紗藍様」の前だからか神妙な顔のままだし、その後ろの山吹は始めからずっとにこにこしているために、逆に表情の変化が分かり辛かった。炎遥に至っては無表情で目すら開けていない。
「返事しないのよ。聞こえてないのか、忙しいのか知らないけど」
「忙しいの? 釣りに?」
「そう。餌もつけてないくせに、何考えてるのかさっぱりだわ。もうちょっと待ってもらえるかな」
やれやれとばかりにため息をついた結麻は、下向き加減の連理がこちらを睨んでいるのに気付いて、ばつが悪そうに居住まいを正した。
「ごめん、やっぱり翠嵐は抜きでいいよ。あとで伝えるから」
「いいの? ……わかった」
紗藍は頷き、鮮やかな模様の紙でできた小箱を手元に引き寄せると、そこから先ほど早稲がふたりに見せたのと同じ見取り図を取り出し、楚々とした手つきでそれを床に広げた。
紗藍の身のこなしは、どこかいつも遠慮がちで腫れ物に触るようだ。振る舞いからして控えめと言うのか、自分とはまるで逆だと思いながら結麻は無意識に自分の手元に目をやった。それにちらと移した視線をゆっくり見取り図に戻した紗藍は、少し長めに息をついてから話を始めた。
「ここは前、連理たちにお願いしたことがある屋敷。だからこうして、かなり詳細な見取り図があるんだけど」
連理に目をやった紗藍は、頷いた彼を確認するとまた視線を落とした。
「連理。ここまで、どのくらいかかるかな?」
「二……いえ、三日」
言い直した連理に、紗藍の後ろで炎遥が微かに目を上げた。今回の編成を見れば、彼はある意味お守(も)りのようなものだ。同行者の能力や経験を斟酌して発言しなければならないことを既に知っている。紗藍は先を続けた。
「依頼者は、ここの家と対立している家の人。話し合いで決着がつかないから、いい加減痺れを切らしたんだって。確かにウチに頼めば、ある意味では手っ取り早いものね」
そんな考えを持つ人のことは分からないけれど。言外にそう言った紗藍は結麻の表情を窺い、彼女もまた同じことを思っているのだろうと見て口元を綻ばせた。
「この家の当主ですか?」
そう聞いた連理に、紗藍は顔を上げて頷いた。
山吹がわずかに目を細めたように見えたが、その主である連理はいつもと変わりない。それが結麻には少し恐ろしかった。
生業であるとは言え、人を殺す段取りをしているというのに「いつも通り」なのだ。これがこの集落、この部族の日常。紗藍が自分の顔を見て安堵の表情を浮かべたのは、そこに彼女がまだ染まり切っていない証だ。結麻にはそれが嬉しかった。
「今回は前金なの」
呟くように言った紗藍に、連理は片眉を上げた。結麻にもそれが異例のことであるのは分かった。大抵の場合、報酬は着手金と成功報酬という形で分納される。はじめに一括して支払われるのは、どんな小さな失敗も許さないという依頼者の強い意思による時だけだ。
「幾らですか」
表情を変えずに聞いた連理に、紗藍は金額を答えた。相場の分からない結麻はただただ驚き、連理もこの時ばかりは少し笑った。
紗藍は見取り図に目を落としたままだ。誰かが口を開くのを待っているかのようなその場の空気に促されるように、連理は言葉を落とした。
「皆殺しですね」
結麻が眉を顰めて顔を上げた。紗藍も浮かない顔で下を見たままだ。ただひとり平然とした顔の連理は、見取り図をつまみ上げた。薄い紙を焼くちりちりという音がし、火に包まれたそれを手放した連理は呟いた。
「炎遥と組んでこの先やっていくおつもりなら、いい経験になります」
「え?」
意味を汲み損ねた紗藍が聞き返す。話の終わりが近いと察したのか、炎遥と山吹が立ち上がった。紗藍と連理それぞれに能力を分け与えている、二人ともーーあるいは「二匹とも」、炎竜。
その衣擦れの音に紛れるように。
「焼き払います」
連理は、そう言った。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
夕食の買い物をしてから帰るという結麻を屋敷の門前で見送り、連理は後ろに控えた山吹を振り返った。
辺りは夕暮れを迎えている。中心街から少し離れたこの場所は静かで、人通りはほとんどない。肩をすくめてみせた山吹を険しい目で睨みつけ、連理は待った。この後、結麻のいないところで伝えられるべき話があるはずなのだ。
「大仕事ですね」
もう笑顔ではない山吹が呟き、連理は苦笑まじりの表情で頭を振った。
「どうかな。見て察することを放棄した奴だ」
「しかし、面倒なのは確かです」
「ああ」
自分があの、燃やした見取り図の屋敷に行った時のことは鮮明に覚えている。その時も確かに後衛という役割ではあったものの、彼は与えられた仕事を模範的とすら言えるほど完璧にこなした。ところがあの家は、どうにか上手く取り繕ってそれを隠し続けているようだ、と風の噂に聞いた。ただそれは連理をはじめ集落の者にはどうでもいいことだ。彼らは請け負った仕事をやってのけた。あとの面倒は依頼者の責任だ。
そして今、また同じ家を標的にした仕事が舞い込んだ。あの場所を知り尽くしている彼に、新米の二人――度会と瀬尾、両家の当主という、何か心もとなくもある編成での仕事。しかもその編成をするにあたり采配を振るったであろう早稲が、伝えるところまでを直々に。
連理の記憶では、あの家は既に標的とは「なり得ない」。自分たちには無関係の後始末しか残っていないはずだ。だがそれも連理にはどうでもいいことだった。彼の家、湯木は古くからの度会派だ。今までも、今も、そしてこれからも。早稲も当然それを知っている。
それだけ揃えば、自分に与えられた本当の「仕事」が彼には簡単に推測できた。あとはそれを確かめるだけだ。
門扉を内側から叩く者がいる。ほら来たとばかりに連理は返事をし、開けられた厚い木戸の中に再び、消えた。
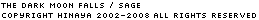 (7)
(7)