vi / Juglans ailantifolia
度会の屋敷が見えてくるより前に、結麻は走るのをやめていた。同じ方を目指す知人に会ったためだ。彼女は相手も同じような状況にあることを聞き、自分の心配はきっと杞憂だったのだ、と胸をなで下ろした。
その名前を連理(れんり)と言う。山吹の主である彼もまた、今回何の「仕事」も割り振られていなかった。しかし結麻や紗藍と違い二十代も中盤にさしかかった彼は、彼が十七になった時に引退を表明した父から山吹を引き継いで五年をゆうに経過しているし、これまでの仕事ぶりも賞賛に値するものだった。そろそろ中堅の仲間入りをして、難しい仕事にも手を付け始めていい頃だ。しかも彼の家、湯木は古くからの度会派なのだ。だというのに彼にも今回何も分担がなかったという。一人で複数を請け負っている者もいる、人手は決して足りてはいない状況でも、だ。
「こう言うのは誤解を招くかもしれないけど、結麻と違って俺ん家(ち)には特別扱いされる理由がないんだよ。良くも悪くも」
そう言って連理は肩をすくめ、腰に両手を置いて地面に目を落とした結麻を見下ろした。彼の方が頭一つ分以上身長がある。
「山吹は何て?」
「別に。最近仕事しすぎだからお休みをくれたんだと思えばいいですよ、ってさ。親父と俺の記憶が正しければ、前回真面目に働いてから今日までの間、満月は四回あったと思うんだけどね? 紗藍様が炎遥を呼び出す前だ」
「相変わらず山吹はのんびりね」
苦笑を漏らした結麻は、ため息をついてから顔を上げた。
それだけの期間何もなかったと言えば、山吹も決して、単に連理に休みを取らせる目的で仕事が割り振られなかったのだとは思ってはいまい。ただそこにある本当の理由に、山吹がわざわざ首をつっこむ動機がないだけだ。しかし主の方はそうもいかなかった。仕事、そしてそこから得る収入が生活に直結する。人間は食べなければ生きられないのだから、そうではない竜のように悠長に構えていることはできない。連理の場合は尚更だ。彼は既に一線を退いた父母を自分一人で養っている。
結麻に仕事が来なかったのは考えてみれば、彼女には養う家族がないから、あるいはまた単に彼女のような経験のない者に任せられるような易しいものがなかっただけだという理由も有り得なくはなかった。だがその意味でも連理は違う。
連理と山吹とは、集落内でも認められる好連携を見せる。そして結麻は、本人の経験は不足どころか無に近いものの、その契約竜は呼び出した時から集落の者に一目置かれている。
眉間に皺を寄せたまま黙って歩く結麻の後ろで、連理は所在なさそうな顔をして手の甲を掻いた。風に葉を揺らした生け垣の陰で小鳥がちよちよと鳴いている。いい天気だ。前を行く結麻の影が彼の手の半分にかかっている。
ふいに結麻が立ち止まったので、彼もそれに従った。顔を上げれば屋敷の門は目と鼻の先だ。
そこにいつも警備の者はいない。瀬尾という反対勢力が事実上潰(つい)えてしまった今は、集落内にそのようなものものしい雰囲気は――少なくとも目に見える範囲では――なかった。
しかし今日に限っては、そこに人影がひとつあった。連理(そして翠嵐)と同じくらいの歳に見えるが見覚えのない顔だ。そしてその影は、砂地に映った背に翼を負っていた。結麻は眉を顰め、反対に連理は明るい表情で手を挙げ彼に声をかけた。
「炎遥」
顔を上げた男の背に翼はなかったが、燃えるような朱色の髪が揺れ、切れ長の橙の瞳が結麻を射抜いた。彼女は無意識にごくりと唾を飲み込んだ。
これが、紗藍の竜なのだ。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
炎遥に案内されるまま、結麻と連理とは屋敷の奥へ向かった。長い廊下を何度も曲がり、離れと呼べそうな部屋に通された彼らは、そこに度会の前当主が待っているのを見た。実質の最高権力者だ。示されるままに彼の前に座った二人は、部屋を出て行く炎遥が静かに引き戸を閉めたのを背中で聞いた。
炎遥の主は紗藍だ。だから彼はこの前当主の小間使いのような仕事をするはずがない。それなのに彼がこうしてこの部屋に通した。紗藍に関係のあることなのだ、と結麻は直感した。前当主――紗藍の父、早稲(わせ)は口を開いた。
「きみたちが来てくれなければ他の者に頼むつもりだった。ありがとう」
「そのようなお言葉、滅相もございません」
膝の前に手をつき、下げた頭をなかなか上げない連理の隣で、結麻は僅かに首を傾げた。
豊かな白まじりの髭をたくわえ、目尻に笑い皺のあるこの男、度会早稲は自分の父と権勢を競い合っていたはずだ。それが自分を前にして、この柔らかさは一体なんなのだろうか。もう瀬尾との確執など忘れてしまったのだろうか。名ばかりではあるが瀬尾の当主たる自分を前に、そんな名など眼中にないとでも言うのだろうか。家名や自分の扱いをどうこう思いはしなかったが、とにかく結麻に彼の物腰と居住まいとは違和感を覚えさせた。
改めて見た早稲の濃紫の瞳が自分を見ているような気がしたので、結麻は慌てて頭を下げた。
早稲は緩く瞬きをして二人に顔を上げるように言い、己の後ろに手を回すと、そこから丁寧に畳まれた紙を取り出した。彼はそれを自分の前の板床に広げ、それから静かに向きを変えて二人に合わせた。
どこかの屋敷の見取り図のようだった。目をしばたたかせた結麻の横で、連理は眉を寄せた。彼はこれがどこのことなのかを分かっているのだ。早稲は連理のその反応に満足そうに頷いて、言った。
「これの後衛を任せたい」
「後衛」
顔を上げた連理に、早稲はもう一度頷いた。後衛ということは、中心になる者が別にいるはずだ。結麻は何も言わず、しかしなるほどという表情で眉を上げた。その「中心になる者」こそ、紗藍なのだ。
連理の反応や、紗藍――当主自らが出向く仕事であることを考えれば、この見取り図の屋敷はかなり名のある家なのだろう。そして今回の仕事は「最後まで」を要求されているに違いない。評決への出席を阻止するために手傷を負わせるとか、人質として差し出された嫡子を取り返して次の手に備えるとか、そういう類いではない。
殺す仕事だ。少なくとも結麻は、そう思った。
仕事の割り振りがないことに不満を持っていた彼女に、それを断る理由はなかった。当然連理にもだ。早稲は再び炎遥を呼び、その見取り図を手渡すと二人を紗藍の部屋に連れていくよう指示をした。
二人を先に部屋から出して、炎遥は引き手に手をかけた。
部屋の中、座ったままの早稲が膝に手を置き、こちらを見ている。炎遥は僅かに目を細め、そして戸を閉めた。
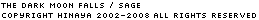 (6)
(6)