v / Veronica persica
家々の灯りが消え始める頃、薄曇りの夜空を見上げて紗藍はため息を落とした。
彼女の隣には炎遥がいる。家の勢力をそのまま形にしてみせたような、集落の中でも一際大きな自分の家の縁側で、彼女はもう一度ため息をつくと、座った自分の周りを柔らかに守るように寝そべった赤い竜の、固い皮膚をさらさらと撫でた。
彼女は確かに、度会家当主の座を継いだ。しかしそれはあくまで名目上のものだ。今は前当主である父がまだ健在である上、部族を統率する立場としては経験も威厳もない紗藍には、この時家の中で開かれている会合に口を出すことは許されなかった。かと言って同席することを禁じられていた訳ではないし、むしろ同席した方が経験を積むという意味では良かったのだろうが、彼女はそれを固辞した。
その代わり、そこには彼女の使いを遣っている。とは言っても炎遥はここにいるので、正確に言えばそれは、炎遥が放った使い《虫》だった。契約竜の中には、自分より下級の、竜の姿を持たない存在を従え使役する能力を持つものがまれに現れる。炎遥がそれだった。
家の中で話し合われているのは、今度請け負った「仕事」の配分だ。かなり高度な技術を要すると思われるもの、多少未熟でも竜を連れてさえいればこなせそうなもの、そういった難易度の違うものがいくつか挙がっている。
その中にはかならず、先日契約を成立させたばかりの結麻に割り振られるものがあるはずだ。紗藍はそれが決まる場に居合わせたくはなかった。結麻がそんなふうに思うはずはないとは分かっていたものの、万一彼女に割り振られたものに彼女が不満を持った時に、それが自分の差し金なのではないかと疑われることが嫌だったからだ。
結麻にあのような話をしたことを、紗藍は少なからず後悔していた。あれではまるで自分が竜をもの扱いしているようではないか。そのように割り切るしかない面があるのも確かだが、彼女は炎遥を簡単に取り替えることなど考えたくもなかった。
父の従えている竜、そして結麻が呼び出した竜に比べれば確かに炎遥は多少見劣りする。しかし彼女は彼を既に、自分の半身として愛していた。虫を使うことができる能力のせいではない。彼は自分を選んでくれたのだし、なにより家名のせいで人々が距離を置く中、誰よりも長く傍で自分を理解してくれる存在になるはずなのだ。
「炎遥」
<はい>
「結麻、怒ってると思う?」
<私には分かりません>
「そっか。炎遥は?」
橙色の瞳をしばたたかせた炎遥は首を傾げて見せ、紗藍はそれに肩をすくめた。
「炎遥は怒ってないの?」
<何をですか?>
「私が『炎遥じゃ足りない』って言ったこと」
<事実でしょうから>
睫毛(まつげ)の目立たない目を伏せた彼に目を細めると、紗藍はぺこりと頭を下げた。
「ごめんね」
<……いいえ>
苦笑した紗藍が立ち上がると、炎遥もまたそれに付き従うように立ち上がる。背伸びをした紗藍を見上げ、そのままふいと顔を後ろにやると、彼は自分の尾の先にふわりと止まった蛍のような光に目を細め、紗藍の肘を鼻先でつついた。
<虫が>
「決まったって?」
腰を屈めた紗藍は、炎遥の言葉を聞き取ると眉根を寄せた。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日が一番高く昇った頃にしかめっ面をして家に戻ってきた結麻は、これでもかというほどに勢いよく扉を閉めた。
両親を失った後彼女が祖父母と共に住み始めたその家はどう考えても立派とは言えない、それどころか集落の中でもかなりみすぼらしい部類に入るものだ。扉の閉まった振動で天井の梁(はり)から落ちて来た埃が、窓から入る光に照らされてちらちらと瞬いた。それが手元の本に散ったのに眉を顰めた翠嵐は、ふっと埃を吹いてから表紙を閉じると頭上の窓枠にその本を置いた。
顔を上げて緑の目を結麻に向けた彼は無言だった。彼女は大きなため息をつくと椅子を引いて乱暴に座った。
「約束」
「『ご機嫌斜めでいらっしゃいますね』」
「嘘つかないでよ」
「じゃあ『もちっとおしとやかにしろ』」
眉間に皺を寄せたまま、来いと言わんばかりの表情で腕と脚を組んだ結麻に頭を掻いた翠嵐は、彼女の向かいに座ると横柄な仕草で頬杖をつき、口を開いた。
「で?」
「私は今回はお役目なしなんですって」
「それで機嫌が悪い訳」
じろりと翠嵐を見た結麻はしばらく黙っていたが、そのうち「そうよ」と呟くと食卓に突っ伏した。
彼らの「約束」は、ごく簡単なものだ。「思ったことは言う」。言わずとも聞こえる間柄だからこそ、それは結麻にとっては重要なことだった。
口に出さない、出されない思いが分かってしまうのはいい気分ではなかったし、それが積もればいずれは面倒ごとにも発展しかねない。特に翠嵐の場合、ほかの竜が契約相手にそうするのと違い、決して結麻に遠慮したり、敬意を(少なくとも「主に対する敬意」は)払ったりしてはいなかったので、多分に皮肉っぽい彼の言葉が直に頭に聞こえると、結麻はちくちくと痛むような、ぴりぴりと苛立つような感覚に陥ったのだ。それを口に出させさえすれば言い返してやることもできるし、その時翠嵐は再びつっかかってくることは滅多になかったので、こうして敢えて言葉として言わせることは彼女には十分に意味のあることだった。
「私、いつまでも仕事貰えないかもしんない」
「なんで」
「分かんない。でもそう思う」
突っ伏したままの彼女に眉を上げ、目を閉じてから欠伸をした翠嵐はしかし、彼女の内心を聞き取った。自分の背負う家名に、皆は見えないふりを装うことに決めたのではないか。何も触らずにいることで、認めずにいることで、いつか誰もがその存在を忘れ去り、そして実際消えてしまうのを願っているのではないか――と。
「人間ってのは面倒臭えな」
「……読んだの」
「聞かれたくないなら隠しとけ」
前髪をぐしゃりと掻いて顔を上げ、結麻は椅子の座面に足を上げた。
本当に聞かれたくなければ隠していた。彼女は俯いたまま、ちらりと目だけを上げて向かいの相手の様子を窺った。
「俺の顔見ても何も書いてねえよ」
「分かってる」
もう一度大きなため息をついた結麻は、食卓に両手をついて立ち上がった。
「私、も一回行ってくる」
「あーあーどうぞ。健闘を祈る」
「嘘つき。仕事が来たら怠(だる)いなって思ってる癖に」
「お前こそ読むんじゃねえよ」
にひ、と笑ってみせた結麻は、そのまま振り返ると玄関を開け放ち、走って行った。
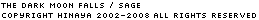 (5)
(5)