iv / Chloranthus serratus
日が一番高い所を過ぎ、徐々に落ち始めている。結麻はため息をついて倒木に腰を下ろした。つい数日前、彼女が翠嵐を呼び出した場所から数十歩と離れていないところだ。今は彼女のほかには誰もいなかった。
自分はそれを望んでいないのに「可哀想だ」と思われることが、どれだけ嫌な気分になるかは彼女にもよく分かっていた。現在権勢を誇っている度会とかつて勢力を二分していた自分の家、瀬尾の当時の当主――つまり彼女の父親だ――が妻と共に命を落としてからの彼女は、常にそういった目で見られていた。弱き者、立場を失った者に対する、上からの優越感の混じった憐憫。
祖父母が育ててくれたが、家の勢力の衰えは曲線を描くことすらなく、あっという間に彼女の家名は過去のものとなってしまった。とは言えその名を背負っていることには変わりがなかったため、彼女は集落の中で「普通」になることを許されなかったのだ。捨ててしまえれば楽なのにと考えたことは数知れない。
ただそれは人間どうしという元来同等なものの間の話で――しかし、考え出せばきりがなかった。翠嵐が出て行ったその日から、彼女は今日で三日同じことを頭の中で循環させている。
彼を人間と同じように、対等に扱おうとしたこと自体を間違いだとは、今でも思っていない。かと言って彼が指摘してみせた彼女の内心に、その通りだと開き直れるとは思えなかったし、思いたくもなかった。ならばそれに代わる理由があるはずだ。彼女は再び大きなため息をつき、空を見上げて目を閉じた。
背後で茂みが音を立て、彼女は咄嗟に立ち上がると飛び退いた。
そこにいたのは紗藍だ。結麻と同い年の、度会家の現当主。今日は周りに誰もいない。結麻は肩をすくめ、先ほどの場所にまた腰かけると隣を彼女に勧めた。
立場のせいで人前で親しくしづらいのは確かだったが、それでも歳の近い彼女は結麻にとっては貴重な友人と言えるのも事実だった。また紗藍の側も、家名目当ての者たちより結麻といる方が肩肘張らずにいられるらしい。ふたりは周囲が思っているよりずっと親密で良好な間柄だった。好敵手としても。
「見たよ。凄いの呼べちゃったね、おめでとう」
「中身はもっと凄かったけどね……」
「そうなんだ」
眉間に皺を寄せたまま、膝の上で頬杖をついた結麻に、紗藍は苦笑した。
「随分疲れてるみたいだし、他のを呼び出して契約をやり直すのもありだと思うけど。扱い辛いと、きつくない?」
「扱い辛いっていうか、見透かされてると思うとやりづらいかな」
ああ、と笑った紗藍は、指先を組むと目を伏せた。
「私も最初それで結構悩んだよ。他人だと思ってると、どうしてもね」
「だって、他人じゃない?」
「違うよ、人じゃないもの。私は炎遥(えんよう)を、自分の体が二つあるようなものって思うことにした。自分の思った通りに動いてくれるんだしね。そしたら結構気楽になったよ。今も外で見張ってくれてる」
「見張る?」
「私が結麻と喋ってると、嫌な顔する人がいるからね……体ふたつあると、便利でしょ?」
無意識に周囲を見回し、しかし「見張ってくれている」のだから誰もいないのが当たり前なのに気付き、結麻は頭を掻いた。
「ねえ、結麻」
紗藍は立ち上がり、座ったままの結麻を見下ろしながら両手を腰に置いた。
「結麻が契約を無事に終えたことと、契約竜があんなのだったこととで、結麻がうちの家に逆らうんじゃないかって人が結構、いるんだよ。皆表立っては言わないけど」
「私はもう家の勢力とか、どうでもいいんだけどな。ただ他の人と同じようにちゃんと仕事ができて、一人前だって認めてもらえれば」
「分かってる。でもそういう風に疑ってかかられてる限りは、結麻も居心地が悪いんじゃない? 孤立って言うと何なんだけど……」
紗藍の言わんとしていることが今ひとつ掴めず、結麻は眉を顰めて彼女を見上げた。
「別に、今まで通りじゃないかな」
「結麻はそのつもりでも、多分そんな簡単にはいかないよ。周りにそんな風に思われてる限り、うちから皆に仕事を回す時に、結麻にはきついのを割り振ろうとする人だって出てくるだろうし、あわよくばその仕事の中で結麻もお父さんみたいにって。私は当主って立場はあるけど、まだこんな歳だし、とりまとめた仕事の配分には口を出せないから」
「やめてよ」
「でも、本当だよ。だからさ、もし良かったら結麻の――」
言いかけた紗藍が跳ねるように顔を上げ、振り返った。茂みの向こうに人影が見え、彼女は結麻にごめんと手を合わせた。
「人、来たみたい。見つかると面倒臭いから、途中だけど」
「……大変だね、家が凄いと」
「ごめんね。もっとゆっくり話せる機会があったらいいんだけど」
頭を下げて紗藍が行ってしまい、またひとりになったその場で、結麻は先ほどまで紗藍の座っていたところにごろりと横になった。
「もっとゆっくり話せる機会」など要らないと思った。彼女の口からその話の先を聞きたくはなかった。
紗藍の言おうとしていたことは、分かる。炎遥《彼女の契約竜》が思いのほか力のないものだったことは、それこそ誰も表立っては言わないが、周知の事実だった。集落中をかけずり回って探した「扉」の割には期待はずれというだけで、山吹などに比べればずっと力のある竜ではあったのだが、それでも彼女に家名と当主の座に見合った最高のものをと考えていた周囲の思惑は裏切られた形だ。
だから彼女は、彼女の背負う家名に恥じないため、その立場に見合う自分であるために、結麻の呼び出した竜を自分に譲る気はないか聞きに来たのだろう。家名に力がなく、しかし手にした力は大きかった結麻とはまるで逆なのだ。周囲の期待に応えなければならない彼女の苦しさも想像できた。
かと言って、その申出を受ける気は結麻には全くなかった。翠嵐は「譲る」対象などではない。そこまで考え、ああ、と呟いて彼女は背を起こした。
何故人間として、対等に扱おうとしたか。簡単なことだった。
相手のことを考えた上での慈悲ではない。祖父母の他界からひとり、集落でも半ば孤立していた自分が、別れを強いられない存在を望んだ。いつも傍にある道具、使える力などではなく、傍にいる「人」を、自分が望んでいた。だから人として付き合いたかった。人であってほしいと願った。
理屈などなかった。言い訳を剥がしてしまえば、理由はそれだけだったのだ。
夕暮れ、西に赤が沈み始めて家路についた彼女は、数軒先に控えた自宅を生け垣ごしに覗いている人影を認めた。顔を見るまでもない。あんな色の頭をした人間はこの集落にはいないからだ。
何の悪びれた様子もない顔で振り返った彼に苦笑して、彼女は歩みはそのまま口を開いた。
「なんで中に入らないの?」
「鍵がないから」
「自分の家の鍵くらい持ってなさいよね」
「くれ」
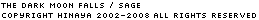 (4)
(4)