iii / Chloranthus japonicus
結麻は、決めた通りにした。
周囲がそれにあまり良い顔をしないのはよく分かっていたが、それでも彼女は自分の契約竜――翠嵐に、人の姿でいることを許した。
決して集落の習わしに唾を吐きたかった訳ではない。ただ(当たり前だが)生まれてこの方人間である彼女にとっては、彼に竜の姿を強いることは不便そうに見えて仕方なかったし、またそうした姿を取らせることは彼女にはさしたる意味を持っていなかった。そしてそのためか彼女には、その場では最早当たり前になっているその習慣が、人間が強いた主従の証であるという認識すらあった。
「でも、契約ってのは持ちつ持たれつの関係よね」
お世辞にもきれいとは言い難い、しかしこざっぱりとはしている一間(ひとま)だけの自分の家で、結麻は椅子の上に足を乗せながら、古びた食卓を挟んだ向かいで座面にあぐらをかき手元に目を落としている翠嵐を指差した。
開け放たれた窓の外、朝の光が生け垣の下にまだらの影を落としている。結麻が翠嵐を呼び出し、契約を結んでから二日目だった。彼女は不機嫌そうな顔で顎をしゃくった。
「あんた、ちょっとふてぶてしくない?」
翠嵐はちらりと目を上げた。どこから調達して来たのか、手元には虫が食った跡も無惨なぶ厚い本が開かれていたが、彼はそれを開いたまま食卓に置くと大きな欠伸をした。
今の彼は他の竜が人の形を許される時と違わず、二十代半ば程度の人の姿をしている。歳を取るという概念のない彼らにとっては、どうやらこの辺りの姿が一番動きやすいらしかった。
呼び出した時に竜の背を彩っていた紅葉の色は、今は髪に反映されている。深い赤の刈り込まれた後ろ頭をぼりぼりと掻いて、彼はそれよりは少し長い黄色の前髪をつまみ、それからそのまま頬杖をつくと若葉色の目を細めた。しかしそれは結麻をまっすぐには捉えていない。
「誰がふてぶてしいって」
「あんたよ」
「よく言うよ。『で、どうしたいのよ』のお嬢さんが」
「応じたのは自分でしょ? 私は懇願はしてないわよ」
翠嵐は肩をすくめ、つまみ上げた本の一頁に空いた虫食い穴に人差し指を通して弄びながら、で、と先を促した。
「お嬢さんは俺に何をして欲しいわけ」
「私の名前を覚えること。『お嬢さん』なんて気持ちが悪いもの」
「名前で呼べって? 変な要求すんな」
彼は自分で広げた穴を人差し指と親指とでつまんで隠し、指先で擦り合わせてから手を離した。さっきからずっとこういう作業をしているのだ。その結果ここより前の頁に空いていた穴は紙が再生して塞がれているが、かと言ってそこに連ねられていた文字までが戻る訳ではない。
「だって『主(あるじ)』なんてのも、余計気持ち悪いし」
「他の連中はそう言うだろ」
まあね、と答えた結麻は、食卓に肘をついてため息を落とした。
「でも、なんか違うのよね……感覚っていうか、皆と。そんな風に上下を押し付けてしまうのってどうかと思うの」
彼女はそのまま食卓に頬をつけ、もう一度ため息を漏らしてから目を閉じた。
「呼び出したこっちばっかりがいい目見てるようで、申し訳ないっていうか……私はそういうの、逆に負い目を感じるのよね。皆を否定するつもりはないけど、悪いことしてるような気になる。虐げてる、みたいな」
翠嵐は驚いたという風に眉を上げ、本を閉じると食卓の隅に寄せた。
「異端児だな。瀬尾の若き当主は」
結麻は眉を顰め、顔を上げた。自分の家のことなど喋った覚えはない。
「私、そんな話してないわよ」
「聞こえるんだよ。俺らと契約をするってのは脳味噌を共有するのと同じだ」
「……いつも覗かれてるの?」
「お互い様だけどな」
結麻は額に手を当て、今までで一番大きなため息をついた。
「私にはあんたの頭の中が聞こえないけど?」
「何も考えてないからじゃね」
そう言って翠嵐はもう一度、鷹揚(おうよう)に欠伸をした。彼の表情は無関心をそのまま顔に貼付けたようで、結麻はそれに心底参ったという顔で頭を振った。
自分が考えることは、今目の前にいる竜には筒抜けなのだ。身内とは言え、隙も何もあったものではない。その上相手の考えは自分には届いて来ていない。本当に何も考えていないのか、それとも――
「『不公平だわ』?」
顔を上げた結麻に、翠嵐は肩をすくめて見せた。
「人間どうしの付き合いとは違うんだよ。お前のお仲間が契約竜を人の姿でいさせないのは偉ぶってるとかじゃなくて、案外その辺に理由があるんじゃねえの」
「だけど私は」
俯いてしまった結麻を見下ろす形で立ち上がった翠嵐は、その場で腕を組んで首を傾げた。表情には何のかげりもない。ただ緩く開いた目で彼女を見ているだけだ。彼は口を開いた。
「『対等でいようとする私は、ほかの人とは違う』。なるほどね」
「……やめて」
「自分じゃ『対等』のつもりなんだろうが、それが特別である前提として端(はな)から俺らを反抗する力のない、弱く同情すべき存在だと思ってるのに気付いてないだろ? お前も他の連中と何も違わねえよ。自分を上だと思ってるって意味では」
彼の語調に悪意は感じられず、しかし何の抑揚もなかった。淡々としすぎた言葉は逆に結麻を傷つけた。彼は先を続けた。
「ただお前の言い分は確かに、気に食わないって意味では特別だよ。慈愛に満ちた人間を演じているお前は満足だろうが、自分をダシに酔われたこっちは最高に気分が悪いんでね」
「そんなつもりで言ってるんじゃ――」
「お前らの稼業だとか、契約で得た力の使い方だとかをどうこう言うつもりはないよ、人間の事情には興味ないからな。俺をどう扱おうと、契約を交わした限りお前は俺の力を好きに使える。それでお前にとっては必要十分だろ? 俺がお前と契約したのは人間扱いされたかったからじゃない。勝手させて貰えそうでこっちにとっても美味しい話だったから、それだけだ」
「やめてよ!」
食卓の天板を拳で叩いた結麻に目を細め、翠嵐は先ほど隅に寄せた虫食いだらけの本を持って玄関に向かった。扉が音もなく閉まり、しかし結麻は咄嗟に顔を上げた。
「声が聞こえる」とは、こういうことなのだ。初めて「聞いた」彼の声に彼女は顔を覆った。
嘲(あざけ)りのような、怒りのような、やるせなさのような、あるいはそれらが混じって濁った靄(もや)のような得体の知れない温度に、時折言葉が混じって流れ込む。耳を介して聴くのとは全く違う知覚の方法。それが「聞こえる」。
とすれば、結麻の言葉を先回りできるほど鮮明に彼女の内心が「聞こえて」いた彼には、この二日間、彼女の奢りが全て見えていたのだろうか。彼女自身も意識していなかった全て、そう思うと恥ずかしさが全ての先に立った。
見透かされている。
主が自分でも知らなかった、あるいは目を背け見ない振りをしてきた己を見せつけられること。自分の内面から自分を否定されること。それは主の経験や年齢に関わらず、反駁(はんばく)を許さない敵を己の内に抱え込むのと同義だ。
竜との契約が長続きしないことがままある理由はそれだった。殊に相手が格の高い、それが故に自己主張が強く同情や憐れみを極端に嫌うものである場合にはその傾向は顕著だ。彼らは主を、契約後も値踏みし続ける。
経験からだと前置きをした長老の言葉が頭を過(よぎ)った。「こういうのとは、たとえ今は契約を結べても長続きしないことが多いのだし」。
誰もが経験することなのだろうか。それとも「こういうの」――彼《翠嵐》が、特別なのだろうか。
結麻は下ろした手に目を落とし、それからきつく握りしめた。
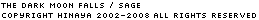 (3)
(3)