xviii / Kalanchoe blossfeldiana
買い物から戻ってきた結麻がほくほくした顔をしていたので、それを見た翠嵐は肩をすくめると、食卓に上げていた足を座面に下ろして本を閉じた。
結麻は持ち物を下ろさず食卓を見下ろしてから、横に視線を移し翠嵐を睨みつけてから顎をしゃくった。今足を上げていた食卓を拭け、と。
翠嵐は渋々といった感じで立ち上がり、流しで台拭きを絞って戻ってくる。それから大層難儀だとでも言いたげに眉間に皺を寄せ、絞ったままの形の台拭きをめくるようにして広げてから、かなり大ざっぱに拭き上げると台拭きをその場から流しに投げ込んだ。
結麻はそれが描く放物線を目で追いかけ、食卓に視線を戻す。そこで翠嵐は手を広げて「もう大丈夫だ」と言わんばかりに天板を示してみせるので、彼女は不満な顔をしながらも、そこに両手に持っていたものを置いてから、ようやく帰ってからの一言目を発した。
「今日もまた貰ったの」
「鍋ごとか」
鍋は返すわよと笑いながら、結麻は翠嵐の向かいに腰掛けた。
「三日に一回くらいかな、こうやってお裾分け貰えるなんて『普通』っていいわね」
「そうかい」
「食費が浮くもの。もちろん私からのお裾分けもするけど……」
そう呟きながら、結麻は鍋にかぶせられていた布巾を取った。それを畳みながら彼女は、そこから立ち上る匂いに顔をほころばせた。
「こんなの、私じゃ作れないわ。見て、美味しそう」
「でも足りないだろ」
「二人で、これじゃ足りないなんて非常識よ。あんたはもう少し、常識に敬意を払いなさいよね」
「やなこって」
結麻は布巾を翠嵐の顔に投げつけると、取り皿を取りに立ち上がった。
結麻と紗藍が悲報と共に戻ってきてからしばらく経つ。その前後で、集落の皆の結麻の扱い方に現れた大きな変化に、彼女はかなり早い段階で気づいていた。
以前なら「瀬尾家」に肩入れしていると見られかねない行為は、誰もが敬遠していた――早い話、結麻は紗藍や連理といったごく一部を除く集落のほとんどの者から距離を置かれていたのだが、今は違う。すれ違う誰もが軽く挨拶をしてくれるし、時にはこうしてお裾分けをくれることさえある。
これがこの集落の「普通」のご近所付き合いなのか、それともかなり目をかけてくれているのか。これまで「特別」しか経験していない結麻にはどちらであるかは分からなかったものの、いずれにせよ有り難いことだった。疎まれない、敵意を向けられないことがこれほどに気持ちを柔らかにするとは。
もしかすると紗藍の行動は、そこまで見越してのものだったのかもしれない。だとすると結麻は少なからず彼女に感謝の言葉を述べたい気にもなったのだが、彼女とあまり顔を合わせたくないのもまた、事実だった。
二人が――と言っても結麻の意見は容れられておらず、彼女はただ反対しなかったというだけなのだが――取り決めた「事実」は、現実には不実でしかない。しかしその不実の事実によって、結麻はこの集落にいることを受け入れられ、あるいは存在を皆に認められたのだ。それこそ自分がもともと望んでいたものではなかったか。ならば自分は一体何を気に病まなければならないのだ? 連理の母に会いにも行ったのに。二口目を運んだ箸を置き、結麻はため息をついた。
翠嵐は相変わらず不作法に、椅子の上で座面にあぐらをかき食事をかき込んでいる。結麻はそれにちらりと目をやり、翠嵐が気づいて箸を止めたのに肩をすくめてみせた。
「何だよ」
「別に……よく食べるなあと思って」
翠嵐は眉を顰めたが、それ以上追及しなかった。
敢えて追及してこないのだ。結麻の頭にあるのがそんな無邪気な感嘆ではないことを、翠嵐も当然知っている。それでも問い質さないのは、何か訳があるのだ。たとえば、彼が「真実」を知っているとか。
食事を終えた結麻は、箸を揃えて置くと片肘で頬杖をついた。その目の前で翠嵐は最後を飲み込み、箸を転がすように置いて足を組み替えてから、自分を見ている結麻に眉を顰め、彼女と同じように頬杖をついた。
「何か用」
「翠嵐、最近隠し事が多くなったわ」
「別に隠してねえよ。言わないだけだ」
「責めてる訳じゃないけど……」
結麻は続きの言葉を濁し、湯飲みの中の冷めた水面に目を落とした。自分が映っている。翠嵐のため息が聞こえた。
「聞きたいことがあるなら答えるけど?」
「話したくなったら話して」
そう言って結麻は立ち上がり、器を重ねてから流しに持って行こうと背を向けたので、翠嵐はもう一度大きなため息をついた。結麻はそれに振り返り、手を振って座るようにと示した彼と手に持った器とを見比べてから、先に流しに向かい、それから改めて椅子に腰掛けた。
「炎遙とちょっと話した」
「いつよ」
「こないだ」
こないだなどという言葉では昨日なのか一昨日なのか、それとももっと前なのかは分からない。しかし怪訝な顔をした結麻を見ても、翠嵐は言い直すことをしなかった。大して重要とは思っていないのだろう、彼はその先を続けた。
「紗藍は思った以上に強(したた)かだ、と笑ってた。当主にふさわしいとね」
「それって」
「それ以上のことは俺にも分からねえよ。紗藍の考えてることが覗けるのは炎遙だけだ」
結局翠嵐も、結麻をすっきりさせるだけの情報を持っていない訳だ。結麻は少しいらだたしげな様子で口を開いた。
「つまり、何も分からないわけね?」
「いや、そんなこたあない」
「じゃあ何が分かったって言うのよ」
「俺はおまえを選んで正解だった」
裏表があるのは好きじゃない、と彼は眉の上を掻きながら、言った。
「私を選んで正解?」
突然何を言い出すのだとでも言いたげに目を見開いた結麻に、ああそうだ、と翠嵐は呟いて肘を顎から外した。
「それとな。今度からおまえは『仕事』しなくていい、全部俺がやる」
「なんで? それも炎遙……紗藍に言われたの?」
「いや俺が決めた。お前の手際の悪いやり方を見てるとイライラする。それよか自分で鮮やかにキメる方が爽快」
結麻はさっと顔色を変え、天板を叩くようにして立ち上がった。翠嵐の前の器が音を立てる。
翠嵐はつまり、自分を無能だと言ってのけたのだ。それが間違いだとは言わない、しかし――
結麻は、座ったまま自分を見上げている翠嵐を睨み下ろし、しかし彼の表情に眉間の皺を解くと、口を一度堅く結んでから肩をすくめ、すとんと腰を下ろした。
「言わないのは許すわ。でも嘘をつくのは反則」
「どうせバレてんだからいいだろ」
「細かいところは分からないんだから、言わなきゃ駄目よ。私が怪我すると、契約してる自分としては困るっていうの? それとも気持ちの上で嫌なの?」
お好きに、と両手を広げた翠嵐に、結麻は苦笑した。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
結局、彼女は翠嵐の申し出に基本的には従うことにした。基本的には、というのは、完全に別行動をとるわけではなかったからだ。
仕事を請けるのは結麻の役目だった。彼女はその内容を翠嵐に伝え、また現地で最終の打ち合わせをするまで一緒だった。
翠嵐は、自分が言ったとおり「鮮やか」に用を終え、戻ってくる。
彼は必ず戻る。そして自分はそれを心からの安堵と共に迎える。その安堵が、以前彼に聞いたように、戻ってこないと「困る」からなのか、それとも「嫌」だからなのか。少なくとも自分の答えはおそらく後者の方だろうと考え、結麻はゆるゆると笑った。
紗藍とのことは、相変わらず何の決着も見ていなかった。あるいは、少なくともこの集落で生きていく限り、決着などあり得ないのかもしれない。
生温い幸せの上を、日々が流れる。
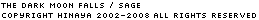 (18)
(18)