xvii / Gentiana scabra
連理の葬儀に彼の遺体はなく、また、彼の両親が心安らかでいられないだろうと早稲が言うので、紗藍と結麻とは参列を控えることに決めた。集落の者が入れ替わり立ち代わり弔問に訪れるのを、結麻は自宅の窓から見ていた。事情は早稲が、紗藍から聞いたままを連理の両親に話しているはずだ。
前を通る弔問客は誰も、葬儀の場に向かう途中にある結麻の家を覗かなかった。また、葬儀の済んだ後も、通りで偶然彼女と顔を合わせても表情を翳らせる者はいなかった。それどころかほとんどの者が同情すら感じさせるような顔で励ましともなんともつかない言葉を投げかけるので、その都度結麻はこれまで遠巻きにされてきた自分の状況を思い、それ以上に連理を思って胸を痛めたが、そうした内心は決して見せないように努めて明るく振る舞い、頭を下げた。
紗藍の提案した嘘は、こうしてこの集落での「事実」になっていった。これが一番幸せに違いない、誰にでも――そう考え、結麻は窓際でため息をついた。真実を知ることは、時として残酷だ。あれから二週間。
それには何とか折り合いをつけたつもりだった。ただ一つだけ、結麻にはどうしてもしておきたいことがあった。あの屋敷を出る前、連理の遺体を運んだ時に一房切り取った遺髪を彼の両親に渡すことだ。紗藍はそれを持ち帰ることをやめさせようとしたので、結麻は従った振りをして、それでもこっそり持ち帰って来た。両親が健在の紗藍には、家族がある日跡形もなく消えてしまった者の想いなど、分からないだろうと思ったのだ。
だから結麻は、それからしばらくして、紗藍には言わずに一人で湯木家を訪れた。
連理と山吹のいなくなったその家は、何も変わっていないはずなのにとても小さく、そして遠く見えた。結麻は以前山吹がよく顔を覗かせていた木戸の前で目を伏せ、頭を振ってから正面に回ると戸を叩いた。
少し時間を置いて出て来た連理の母親は白髪まじりの頭に憔悴しきった顔で、しかし客が結麻であることに気付くと僅かに顔を強ばらせた。結麻は彼女に深々と頭を下げた。
「すみません、急にお邪魔してしまって」
「何か」
愛想のない返事は予想していた通りだ。紗藍の考えた「事実」をこの女性が信じていたとしても、目の前にいる女は連理が死ぬ一因だったのだ。もうひとりが度会家の当主であるなら、怒りをぶつけるのは結麻に対してしかないだろう。これから何を言われても、言い返さないつもりだった。そうして遺族の悲しみに押し潰されたとしても、それしか結麻には誠意を見せる方法がなかった。
通された居間で形通りの挨拶をし、結麻は持って来た遺髪を取り出した。
「これを」
結麻は遺髪をくるんだ白い紙を自分の前に置き、開いて見せたものを再び包んでから床の上で滑らせ、相手に差し出した。連理の母親は、それに目を落としてから顔を上げた。
「これは」
「連理の遺髪です。申し訳ありません、それだけしか持ち帰れませんでした」
そうですか、と呟いた彼女は、畳まれたままの紙にそっと手を置き、もう一度呟いた。
「そうですか」
彼女の頬を、涙が一筋伝って落ちた。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
連理の母親は涙を拭くこともないまま、紙を開いて黒い遺髪を愛おしそうに撫でながらしばらく黙っていたが、やがてそれを握りしめ、嗚咽を漏らし始めた。彼女の手の下で、白い紙がくしゃくしゃと音を立てた。
結麻は何も言わず、言うこともできずに、ただそれを黙って見ていた。「事実」を貫き通す方が幸せだ、と結論づけたはずだ。しかし全て話してしまいたくてたまらなかった。たとえそれが残酷すぎる真実だったとしても、嘘で慰められることなど遺族が望むだろうか?
結麻は意を決し、顔を上げると口を開いた。
「あの――」
「分かっております」
え、と眉を顰めた結麻に、彼女は顔を上げないまま先を続けた。
「連理の負っていた本来の任務を、私どもは聞いております」
「本来の……」
「度会家の勢力を確固たるものにするために、瀬尾の家名を負う者を根絶やしにするようにとの旨、お屋形様に仰せつかったとあの子は申しておりました。そのようなことを、たとえ家族とは言え漏らして良いものかと主人は苦言を呈しておりましたが、あの子は」
彼女はそこで言葉を詰まらせ、結麻は眉根を寄せたまま、下に目を泳がせた。
この女性は、連理が結麻のために体を張ることなどあり得ないことを知っている。では彼女は、真相をどうだと推測しているのだろうか。連理が任務に着手して、その過程で結麻が彼を返り討ちにしたのだと思っている可能性もない訳ではない。あるいはそう思い込むことが、今一番怒りをぶつけやすい方法だろう。だとすればここにとどまるのは危険だろうか?
しかし立ち上がりかけた結麻を手で制し、彼女は大きな息をついてから、遺髪を紙に包み直して前に置いた。
「結果がいずれであるにせよあの子は、度会家のために死んだのです。本望でしょう。天が生き延びることを許したあなたは堂々として、何も心配しなくて良いのよ。遺髪のことは心から恩に着ます。本当にありがとうね」
この女性は、真実を知っているのかもしれない。あるいは別の「事実」を真実と誤解しているのかもしれない。それでも彼女がそれを望むのなら、結麻が真実を押し付けることはできないだろう――彼女はそう考え、姿勢を正すと深々と頭を下げ、連理の家を後にした。
帰り道、結麻の後ろを夕陽が照らし、前に彼女の影を長く作っていた。人通りは、ない。
以前、こうして前に伸びる影を見た時には、隣に人がいたのではなかったか。それは連理ではなかっただろうか。彼女は立ち止まり、自分の横に目をやった。
そこには誰もいない。連理は死んだのだ。
彼がたとえ、命令に従い自分の命を狙っていたとしても、そんなことはどうでも良かった。
二度と彼は横に立たない。目頭がじわりと熱くなった。
「なんでいないのよ……」
聞き取れないくらいの声で呟いた結麻は、その場にしゃがみ込んで下を向いた。前で砂を踏む音がし、彼女は顔を上げないままその相手に、投げやりに言葉を放った。
「なんでいなくなるのよ」
「俺に当たるなよ」
結麻は顔を上げ、彼女を見下ろす翠嵐に険しい目を向けてから口を開いた。
「必要な時に、隣にいなさいよ」
「あいつの代わりにか? ごめんだね」
「じゃあ何しに来たのよ」
翠嵐は肩をすくめ、答えた。
「迎えに来た」
ほら、と彼は手を差し出した。
結麻はそれをしばらく睨みつけていたが、そろそろと手を伸ばした。そうして触れた手を引き彼女を立ち上がらせた翠嵐に結麻は縋(すが)り、場所柄もなく大声を上げて泣いた。
彼女が両親を失ってから、人前で泣くのは初めてのことだった。
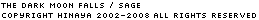 (17)
(17)