xvi / Rosa banksiae
「結局、紗藍様は結麻殿がお考えだったより遙かにしたたかでいらっしゃった、それだけのことだ」
植え込みが燃え上がる葉を散らす前庭、そこに面した渡り廊下の手すりに外向きに腰掛け、炎遙は視線だけで庭を浚(さら)ってから目を伏せた。
庭に無造作に散らばった屋敷の者らの遺体は無惨に焼けただれ、中には原形をとどめていないものすらある。翠嵐は炎遙の隣にいたが、そんなものは見たくもないとでも言うように、木の枝にとまる鳥にも似た不安定な姿勢で手すりの上で庭に背を向けていた。彼はそうして自分の左膝に頬杖をついていたが、炎遙がそれきり何も言わないので、大きなため息をついて口を開いた。
「人間どうしってのは便利だな」
「なぜ」
「理由だけならいくらでも嘘をつける。互いにとって幸せな嘘を」
そう言って翠嵐は屋敷の奥に目を細めた。もう誰の気配もない。この屋敷で生きている人間は、今や結麻と紗藍だけだ。庭を染める炎に照らされた炎遙は、薄暗い奥を見つめる翠嵐の言葉に肩を竦めた。
「信じてこその嘘だがな」
「俺は結麻が幸せならそれでいいよ」
「主が騙されていても良いと」
翠嵐は僅かに眉を上げ隣に目を移しかけたが、やめてそのまま下に落とした。
そこに転がり、冷たくなり始めた連理の体から、小さな光――炎遙の「虫」がふわと離れた。翠嵐はそれを目で追い、肩をすくめて、答えた。
「そうだよ」
手のひらに呼び戻した虫を軽く握り、炎遥は目を伏せた。
「秘密で縛る」
「あ?」
「紗藍様はまこと当主にふさわしいお方だ、と」
「だろうね。俺は結麻に呼ばれて良かったよ。そっちの当主とは反りが合わなそうだ」
「私もそちらの当主の直情ぶりは気に入らない。ちょうど良かったな」
腰掛けなおした翠嵐は、大袈裟に二度目のため息をついて脚を投げ出した。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
結麻は、外で火の爆ぜる音しか聞こえないその部屋で、紗藍と相対して座っていた。
紗藍は血のついた小刀を自分の脇に置き、手を拭った布をその上に被せて、姿勢を正したまま結麻を見ている。対する結麻は目を伏せ、自分の指の付け根をなぞるように目を泳がせていたが、やがて間が保たなくなり、顔を上げた。
「紗藍は、それで良かったの」
「仕方がないもの。ここに果たすべき仕事がなくて、連理は別の意図を持っていた。でもそれは私の与(あずか)り知らぬ任務だった。父上にも聞いてない、彼の勝手な行動」
「だけどそれは、伝えると紗藍が動揺するからって早稲様が……」
「それならそれでいいの。私は知らなかったっていうことが重要なんだよ。私は結麻が大事」
だから、と寂しげに笑みを浮かべ、紗藍は首を傾げてみせた。
この無人の部屋にたどり着いてから、紗藍は連理に、彼が山吹と共に結麻を殺すつもりであるということをはっきり聞いたのだという。彼が言うには、これまでと違い翠嵐を呼び出した結麻は度会家に対する危険を孕(はら)む度合いが格段に高まったので、彼女が仕事に慣れ、翠嵐との関係が密になってしまう前に始末をつけておくことが、今後の集落と家にとって肝要だということらしい。
この部屋に紗藍を連れてくることで、外からは「侵入者が当主の部屋に到達した」という事実、つまり「当主が命を奪われた」と考え得る形を整えた上で、連理が結麻を始末する。そしてその遺体を屋敷の者らと一緒に焼き尽くし、集落に戻ったら、結麻は任務中に事故で命を落としたと報告するーーそれが連理の語ったこの任務の真の姿だ。
結麻が屋敷の外にいる間、あるいは出て来た時には山吹が。中では連理が結麻を討ち取るつもりであったらしく、連理は紗藍にここに残っているよう肩を押して彼女を座らせた。そして彼が部屋を出ようと背を向けた時だ。
「私、無我夢中で」
紗藍は目を伏せた。その視線の先には、血に染まった手拭いがある。結麻は口を固く結んだ。
紗藍は続きを言わなかった。しかし聞くまでもなかった。
山吹が死んだ。彼の主である連理が死んだからだ。
そして連理が死んだのは、紗藍が刺したからだ。
この部屋の、結麻が入って来たのとは別の方向に開く出入り口に、重たい色の血だまりがあった。これが連理のものなのだろう。彼はそこから、瀕死の体を引きずり結麻が使った通用口の方へ向かったのだ。そして、目的を果たさずして死んだ。
彼の遺体は今、どこにあるのだろう。結麻は視線を再び落とした。
紗藍はこうして、この部屋で起こったことを淡々と話してみせた。その間彼女が手元の小刀に目をやったのは、連理を殺したと言った時の一度だけだったし、彼女の様子も屋敷で打ち合わせをしている時のような澱(よど)みないものだったので、結麻は彼女の言うことはおそらく真実なのだろう、と思った。
しかしそれが真実だったとしても、連理が死んだことも事実だ。まさか紗藍が殺したなどと正直に報告できる訳もない。結麻は項垂(うなだ)れた。
「ねえ結麻」
紗藍は目を伏せたまま呟き、顔を上げて先を続けた。
「連理の話した筋書きの、結麻と連理を入れ替えればいいと思う」
「連理が事故で死んだって? そんな」
「私たちが未熟だった。私たちを守って彼は死んだ。彼の名誉も守られる」
この状況と、彼女のしている提案と、それから最初この部屋に結麻が入ってきた時のうろたえを見せた彼女とを比べて考え、結麻は今の紗藍の様子に反論を許さぬ、脅迫めいた空気を感じた。とは言っても竜と主との間のようには行かず、目の前の相手が何を言っているかは頭に響いてくる訳ではない。
相手が人間だから当たり前のことだが、紗藍の心の奥底にあるものは結麻には何かどろどろして重たいもののように思え、そしてそこまでしか分からなかった。前はこんなことはなかったはずだ。育ちの良いおっとりした紗藍は、結麻にとっては純粋さの象徴に近いものですらあった。その彼女が。
人を殺すと、人間は変わってしまうのだろうか。紗藍は連理を手にかけ、変わってしまったのだろうか。それともこれが紗藍の本質で、結麻が今まで気付かなかっただけなのだろうか。
紗藍は結麻から目を反らさない。それが逆に、彼女に嘘――あるいは隠しごとがあるのだ、と結麻に感じさせた。
それだけ分かれば良かった。
結麻はため息をつき、わかった、と答えた。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
屋敷のある丘の周りの集落から、様子を見に来たものが竹の根を踏むのが結麻には聞こえた。
ふたりは人のいない道を選び島の端まで移動すると、半ば白み始めた空の下、炎遥と翠嵐をそれぞれの内に収めて岸を離れ、家のある集落を目指した。
紗藍は一言も喋らなかった。結麻も何も言葉を発しなかった。疲れているはずなのに、全く眠気はなかった。
結麻はただ、家に帰ることだけを考えていた。ほかに人のいない、粗末だけれど落ち着く部屋で、翠嵐に腹の立つ軽口を叩かれること。負けずに言い返して、諦めた翠嵐におやすみを言って眠ること。
おかしなことだが、それが一番心が休まる気がした。
とにかく早く日常に戻りたかった。ただ、それは無理な話だということも、分かっていた。
左の人差し指の爪の間に、連理を運んだ時についたのだろうか、血が乾いてこびりついていた。
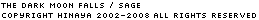 (16)
(16)