xv / Zinnia elegans
いかにも面倒臭いといった感じに頭を掻いた翠嵐は、後ろから見ても分かる大きなため息をついてから振り返った。
それで、と肩をすくめた彼の目の前、今しがた結麻と彼が侵入してきた通用口の方。人が来た様子はなかったが、それでもそこには人影があった。
「いつ気づいた」
「入る前」
目が合うなり問いを投げて来た相手にそう言いながら、翠嵐は板葺きの床を指差した。
「相性がいいんでね」
連理は俯(うつむ)き、笑い声を漏らした。勿論明るいそれではない。彼は顔を上げ、腰から一振りの刀をすらりと抜いて翠嵐につきつけ、言った。
「交渉をしないか」
「こういうのは脅迫っつんだよ」
「いずれでも構わん。応じる気があるかどうか答えろ」
喉元で光る切っ先に目をやり、翠嵐は再び大きなため息をついた。彼が手を上げ、その刀を蚊でもやるように脇に除けても連理は何も言わず、しかし目線も動かさなかった。連理は翠嵐の次の言葉を待っている。翠嵐は目を細めた。
「俺はこっちに出て来てから、そりゃまあいろいろ新しく頭に入れた」
連理は返事をしなかったが、翠嵐は構わず続けた。
「しかし残念ながら好みってのは変わらないのな。俺は、嘘つきと見下し目線の奴は生まれた時から嫌いだね。自分は除いて」
眉を上げた連理は、翠嵐を睨みつけたまま刀から手を離した。
銀色に光る先端は、使い込まれた床板に鋭く傷をつけた。
しかし二人とも、それを見てはいなかった。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
翠嵐の記憶から引き出した屋敷の内部図をたどり、結麻は追っ手を払いながら当主のいることになっている部屋へ向かっていた。
その途中も人は奥からは来ない。来るのは外からの追っ手ばかりだ。それが結麻には、見てもいないものを確信に近づけていた。「ここに当主はいない」。つまり、自分はこの仕事を成功させることができない。成果を持って帰り、皆に自分を認めさせることができない。
結麻は走りながら、腕で目元をぐいと拭った。煙が染みたのだ。そうに決まっている。磨かれた床は外から灰が飛んで来てはいるが、艶があり美しい。こういう廊下を割と最近歩いた。度会の屋敷だ。
目的の部屋の前にたどり着き、後ろを振り向くとそこには誰もいなかった。いずれやって来るのだろうが、今いないのならいい。結麻は躊躇うこともなく引き戸を開けた。
結麻が思わず名前を呼ぶと、紗藍は顔を上げた。彼女の手には小刀が握られている。
だがそれは結麻に向けられることはなかった。彼女は、手から滑らせたそれが床を打って音を立てると、糸が切れたように両手で顔を覆い、膝から崩れ落ちた。
ほかには何の道具も持っていないようだ。彼女のことだから演技でもないだろう。少なくとも自分ではよく知る、親しいと思っていた紗藍にまでそんな目を向けなければならない自分が情けない気がして、結麻は己の手にあった小刀を元の位置に戻し、紗藍の前に膝をつくと、彼女の顔を覗き込んだ。
「紗藍、大丈夫」
「結麻。私、あの」
紗藍の言葉はしゃくりあげながらのもので、ほとんど聞き取ることができなかった。それでも彼女が拭った頬に、手から移ったものを見て結麻は察した。この部屋にそんな様子はないから、ここに来るまでのことだろう。紗藍は人を傷つけたのだ。あるいは、殺したのかもしれない。
それが仕事であるはずだ。九十九を厭いはせぬ。しかし紗藍にまだ早すぎたのか。それとも「当主」が重すぎたのか。あるいは――
「ごめん、結麻」
紗藍はそう言ってもう一度目を拭った。上げた彼女の顔は誰かの血で彩られている。それでも結麻は彼女の目に敵意を見いだすことはできなかった。
結麻は首を振った。紗藍が何を詫びているかは分からなかったが、それでも首を振って、結麻はできるだけ笑顔で言った。だがそれは苦笑にしかならなかった。
「帰ろう、紗藍。帰ってゆっくり話そ、ここは何がなんだか」
「連理を……」
紗藍は再び俯いてしまい、ああ、と肩をすくめた結麻は上を仰いだ。
天井があるので当然空は見えない。しかし仮に見えたとしたら、そこには山吹が舞っていることだろう。結麻を、この屋敷もろとも焼き尽くすために。屋敷の中に入った後は、自分のことで頭がいっぱいで考えが及んでいなかった。だが放っておく訳にはいかない。
紗藍は度会家の当主だ。彼女の言うことなら連理も聞くかもしれない。そういえば姿がないのに気づいて部屋を見回し、結麻は紗藍に尋ねた。
「連理に言ってよ、戻ってからはっきりさせましょって。そっちの方が皆もいるし、いいと思う、私は逃げも隠れもしないし。このままじゃ紗藍まで危ないじゃない、連理は?」
紗藍は答えず、伏せた自分の頬にそっと手を触れ、それから顔を上げると口を開いた。
しかし彼女の声は聞こえなかった。屋敷の中に回った炎が突然大きくなり、爆ぜる音にまぎれてしまったからだ。その音の中に、結麻は叫び声を聞いたような気がした。人のそれではない。もっと、大気を揺るがすような低く、音にならないが「聞こえる」、そんな声だった。
背筋が下から上へ、すうと冷えた。何か大きなものが吸い込まれていくような、それに僅かながら引っ張られるような、経験したことのない感覚だった。翠嵐を呼び出した、彼が現れたそのときと逆の感覚だ。
現れる、その逆。
今、上にいるもの。
確かめに行こうと走り出しかけた結麻の腕を掴み、紗藍は彼女を制止した。いつも控えめすぎるような紗藍には似合わない強さで、結麻は驚いて足を止めた。
「行かないと、外で」
「行かなくても分かるから」
「山吹が……」
「山吹が、死んだの」
紗藍は結麻を離さなかった。腕も、視線もだ。今はもう、この部屋に入って来たときのような頼りなさは全くない。目を見開いた結麻に、紗藍はもう一度言った。
「山吹が死んだんだよ。彼の主が死んだから」
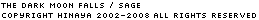 (15)
(15)