xiv / Mahonia japonica
結麻は植え込みの陰を選びながら、さてどうしたものかと頭を掻いた。そしてその後ろで、翠嵐はまったく隠れようともせず、立ったまま欠伸をすると涙を拭った。
結麻たちがまだもとの場所にいると思っているのか、それとも屋敷を迂回して裏側に逃げると踏んで待っているのか、はたまた二人の居場所には気付いているが屋敷に火をかけることはできないでいるのか。いずれにせよ新たな一手を繰り出してくる様子はなく、相変わらず羽搏く翼に火の粉を纏った山吹は、先ほどから遥か頭上を旋回しているだけだった。
彼がそこにいること自体はあまり歓迎できることではなかったが、それでも今は竹林に身を潜めていたさっきよりは安全だと考えていい。方角を確認し、結麻は翠嵐に屋敷の間取りを聞きながら侵入口を探っていた。
屋敷は外廊下を何人もが落ち着きなく行ったり来たりして、上がる声も随分慌ただしいようだった。その周辺で何か面倒が起きたのだろう。例えば、紗藍たちが見つかったとか。しかしお陰で皮肉なことに、別の場所から新たに侵入する者に対する警備は手薄そうだった。
紗藍には連理がついている。彼は自分に対するのと違って紗藍のことは、度会派の一翼を担う湯木家の当主として――もしかするとそれ以外の理由でも――体を張って守ろうとするだろう。それ以前に、これまで数年の経験がある彼がついていながらそこまでの事態に陥ることも、結麻には考え辛かった。そのため二人が見つかったのが騒ぎの原因だという推測は、結麻には我ながらあり得ない気がしなくもなかったが、それはここで考えていたところで答えが出ることではない。
だから彼女はとにかく中に入ってみることにしたのだった。立ち止まっていても行き止まりが迫ってくるだけだ。
「あそこからなら簡単に入れそうね」
結麻は人気のない勝手口に目を細め、意見を求めるように後ろを振り返った。それに翠嵐は肩をすくめ、答えた。
「好きにすれば」
「好きにしていいの?」
「駄目っつっても聞かないでしょうが」
結麻はため息をつき、植え込みから足を踏み出した。
本当に駄目だと思っているなら、翠嵐はそう言うはずだ。山吹のことを言いかけた結麻の言葉を遮った先ほどのように。だから今はこれでいいと、あるいはこれでもいいと思っているのだろう。もう一度振り返ると、彼は結麻のすぐ後ろで、頭上遥かに姿が見える山吹を見上げていた。
「翠嵐」
「あ?」
「はぐれないでね」
「お前がな」
そうねと笑った結麻は、勝手口の引き手に手をかけ、そろそろと戸を開いた。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
こんな風にしているのは彼女のような稼業の者には似つかわしくないことのような気がしたが、それでも屋根裏にうまく入り込むような通気口らしき穴も見当たらず、仕方がないので結麻は板葺きの廊下を歩いて行った。
使用人だけが使うのだろう、見渡した周囲は特別散らかっている訳ではないが、壁沿いには箱が無造作に積み上がっている。飾り気も、ろくな明かりもない長い廊下だ。結麻が振り向くと、少し身長のある翠嵐はしきりに上を睨んでは天井に手をついたりしていた。ぶつかる高さではないが、圧迫感がある。
ここは屋敷の内側を縫うように走っている廊下なので、床板をはがしでもしなければ、下にも入り込むことはできそうになかった。だから結麻は仕方なく堂々と廊下を歩いている訳なのだが、外側の渡り廊下はそれなりに立派なもので、庭にも面し、見た限り中腰で下を歩けるくらいの高さもあったはずだ。
紗藍たちはおそらく、屋内にいる人の目を避けるため、そこを通って目的の部屋の一番近くまで行き、屋敷の内部を通るのはできる限り短い時間で済ませようとするだろう。そしてこの屋敷の様子だ。二人が外にいる間に見つかったので、その周辺が騒がしい代わり屋敷の奥は閑散としている――のかも、しれない。
経験のない自分の考えることだから、結麻にはその推測が絶対に正しいという自信もなかったが、さっきよりはそれがあり得ることのような気がしたし、また、紗藍たちが今自分のいる廊下を通っていないことだけは少なくとも、確信した。何せ静かすぎる上、手負いの者が倒れている様子もない。
それにしても、と辺りを見回す。
あまりに人がいない。拍子抜けを通り越して気味が悪いほどだ。この家は近辺一帯を領地としており、結麻たちの集落では一番大きい度会家が足元にも及ばないほどの権勢を誇っているという話だった。それがたった二人の侵入者のために、これほど内部を空にしなければならないことなど、あるだろうか。
それよりはもっと自然に考えられる理由があった。「もともとこの屋敷に人は多く詰めてはいない」。しかし、そうだとしたらその現実は「権勢」とは相容れないのではないか。
山吹が自分に牙を剥いたことから、自分が連理をはじめとする集落の者に、相変わらず疎まれていることや消されようとしていることは分かっていた。だからこそ彼らを見返す手だてとして、今回請け負った仕事を意地でもやりぬいてやろうと思い、屋敷の塀を飛び越えて来たのだが、実際中に入ってみると「仕事」自体にも辻褄の合わないことが多かった。
自分を消すというのはついでだとかおまけだとか、良い機会だから便乗で、だとか。そう考えたとする。
この家が落ち目であることに気付かず、依頼者は結麻たちのところへ仕事を持って来たのだろうか。そしてそのことに紗藍の父である早稲もまた気付かずに、今回の依頼を娘の華々しい初舞台にしつらえたのか。だがそんな間の抜けた話があるだろうか? 早稲は前回ここに侵入した連理たちの報告を聞いているはずだ。そこから現在のこの家の情勢も推して計れるというもの。報告者が嘘をつくとも思えない。
あるいは、以前連理たちがここに来て遂げた依頼は、実際は今日言われたものと同じだったのではないか。当主が存命であると勘違いした新しい依頼者から前払いの報酬を受け取り、形の上で任務を果たしたと見せかける詐欺まがいの仕事だったのだろうか。そんな信用を失墜させるようなことを早稲がするとは考えられなかった。
では、もしかすると依頼など実際はなく、この任務そのものが、集落の者が自分を消すためにでっち上げた茶番なのだろうか――三つ目の可能性が頭をよぎり、結麻は眉を顰めた。順を追って考えたせいか、それが一番真実味を帯びている気がしてならなかった。止めない歩みが自然と大股になった。床板がぎしぎしと鳴った。
そうした彼女を後ろで眺めながら、翠嵐はただ結麻が目指す当主の居室への道だけを、そこを右だ次は左だと指示するだけだった。とは言え結麻は彼に頭の中を見せじとしている訳でもない。結麻の疑念は彼にも伝わっているのだろう。それでも彼は何も言うことはなかった。
その最後の曲がり角の先は、外廊下から繋がる廊下に接続している。外からの明かりが突き当たりに見えた。
月明かりにしては明るすぎるのは、周囲を火が囲み切ってしまったということだろうか。ただ何であれそこまで出れば、いくらこの屋敷に人間が少なかったとしても、警戒態勢にある者にはおいおい見つかってしまうだろう。
紗藍たちがどこにいるのかは分からない。だが今の結麻にはそんなことは最早どうでもいいことでしかなかった。
この屋敷には、当主がいるのかいないのか。自分が仕事をやり遂げられる可能性が――仕事の「標的」が、存在するのか。
自分が集落の者に認められることは、あり得るのか。
自分の存在を皆に認めさせることは、できるのか。
結麻の顔は険しさを増し、大股ももう「歩き」とは言えない速さになった。
後ろに手を回して刀身を露(あらわ)にした二振りの短刀を、結麻は自分の両手にそれぞれ逆手に握りしめ、前に構えた。そして彼女は後ろにいる翠嵐を振り向くこともなく、周囲の炎を映して山吹色に染まった廊下の合流地点に向かって走り出した。
翠嵐はそこで立ち止まったまま、彼女を追うことは、しなかった。
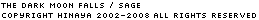 (14)
(14)