xiii / Ageratum houstonianum
「山吹」
呆然と空を見上げ、結麻は呟いた。
裾野の方で、背の高い所に生えた葉が橙に染まり燃え上がった。その上を悠々と旋回した炎と同じ色の竜は、家の前を通るたびに出て来ては世間話をして笑い合った、祖父母亡き後の結麻をことさら気にかけてくれた、集落のどの人間よりも優しかった、あの山吹だ。
結麻はその場を動くことができなかった。
その結麻を夜空から見下ろし、山吹は大きく羽搏いた。長い首と尾はしなやかに、鋭い目で下を見下ろしている。集落にいる時の姿とは違う、紗藍の屋敷で会った時の姿とも違う。あれが本来の彼だ。結麻はそれを見たのは初めてだった。
固い皮膚に覆われ、ところどころ筋状に臙脂(えんじ)の斑が走る体に、燃えるような色の瞳の中で、瞳孔は炎を受け酷く細い。空翔る道具としてはかなり重そうに見える山吹の分厚い翼が風を叩く音は聞こえなかったが、それでもその姿から結麻は咄嗟に片足を引き、腕で顔を守った。 熱風が来る。
彼女の周囲で、下草が悲しげな声を上げて炭化した。しかし彼女に吹き付けたのはそんな烈しいものでなく、何かに漉(こ)された後のようなぬるりとした風だ。吹き返しに煽られた髪が踊って視界を遮り、それを払い退けると結麻は目の前に人影を見た。やや上に顔を向けたまま前に出した右手を下ろしかけた彼は、翠嵐だった。
彼は僅かに顎をしゃくった。下がれというその合図に結麻は素直に従った。今山吹と一人で相対しても、この距離だし、その上自分はただの人間だ。彼女は相手に傷ひとつつけられはしないだろう。何より彼女はそれを望まなかった。相手は山吹なのだ。彼女は何の手出しもできなかった。する気になれなかった。したくなかった。平静を保とうとしても、体中を波のように動揺が走っていた。
「翠嵐」
ぱちぱちと火の爆ぜる中、辺りは燃え始めた足元から照らされ、明るい。頬に感じる熱は炎のものだろうか、それとも自分のか。結麻が絞り出すように口を開くと翠嵐は振り向いた。彼女はすと息を吸った。
「山吹は――」
「駄目だ」
続きを聞くこともなく言葉を一蹴した翠嵐に、結麻は思わず口ごもった。
そんなことは分かっている。山吹がああして攻撃をしかけてきたのは彼自身の選択ではなく、連理の、そして集落の――もしかすると全体ではないかもしれないが、少なくとも湯木家を含む一部の――度会派の意向に沿っただけだろう。しかしあの集落では、翠嵐を除き竜はおしなべて、主に対し絶対の「従」だ。そして山吹はその集落で湯木家に代々仕えて来た、筋金入りと言って良いほどの従。家の敵とも言える瀬尾家の当主を目の前に、主の命を受け、それでも可哀想だからなどという翻意は望めない。
だが、だとしたら今までの山吹は一体なんだったのだ。自分はこうしていつか燃やし尽くされるために、敢えて手折られずにいたと言うのか。山吹はいずれそうなる可能性も知っていながら、それでも自分にあのように接していたのか。
山吹は自分を、嘲笑っていたのだろうか。彼の優しさだと結麻が思っていたものは、いつか連理がその命を下すまでの戯れだったのか。その考えを受け入れることは、彼女にはとても、すぐになどできることではなかった。
足元ががくんと震え、結麻は辺りを見回した。張り巡らされた竹の根が脈動している。いつの間にか炎は弱まり、周囲の明るさも先ほどまでにはない。しかし爆ぜる音だけはまだ続いているし、先ほどより激しい気すらする。
空を見上げた結麻はその訳を理解した。翠嵐を呼び出した時と同じだ。視界を、恐ろしい勢いで成長する竹が遮っている。見渡す限りではこの丘全体がそうだった。ほとんどないと言って良い隙間から、二人の姿を見失ったふうの山吹が旋回しているのが見えた。体からぱらぱらと落ちる火の粉が、遠目に美しかった。
「逃げるぞ」
振り返った翠嵐は、やれやれといった感じで肩をすくめてみせた。それはあまりにいつも通りで、結麻は思わず呆気に取られてしまった。彼には慌てるということがないのだろうか。それともこんなことは想定の範囲内だったとでも言うのか。
とにかくその、ほんの些細な彼の態度のために、自分の今の状況が打って変わって何でもないことのように思え、場違いとは分かっていたが結麻はおかしくなった。彼女はくすりと笑うと彼と同じように肩をすくめ、返事をした。
「いやよ」
「あ? じゃあどうするんだ」
はたと気付いた顔をして、そうね、と結麻は人差し指で頬を掻いた。周囲は再び火に囲まれかけているというのに、今の彼女には焦り直す気がまるで起きなかった。一人ではないことがこれほどにも余裕を与えてくれるものか。自分でも不思議だったが、何であれ有難いことだ。慌てるのは全て終わってからで十分間に合うのだから。
冷めた頭で、彼女は考慮に入れなければならないと思われる要素を一つずつ並べていった。
山吹。連理。湯木家。度会家。早稲。紗藍。集落の皆。今回のもともとの任務。
翠嵐。そして瀬尾結麻、つまり自分。彼女は目を細め、顔を上げた。
「皆に認めて貰わないことには、居場所がないのに変わりはないわ。それはここで死んでも、逃げて死んでも同じこと。それなら相手が準備してある逃げ道、皆の真正面に続く道を、意地でも自分のものにしてみせる。誰にも文句は言わせない。私の活路はその一つだけよ。手伝って、翠嵐」
その言葉にこれでもかというほどに大きなため息をついた翠嵐に背を向け、結麻は屋敷の方へ走り出した。
背後で項垂れた彼は、決して落胆した顔などではなかった。それどころか――幾分苦々しそうにではあるけれども――笑っていた。
翠嵐は山吹のような「従」ではない。それでも自分の選んだ道を絶対に支援してくれる。彼女はそれを思って満面の笑みを浮かべ、屋敷の塀に足をかけると一気にそこを飛び越し、紗藍達が見つかって混乱のさなかにある屋敷の庭に飛び込んだ。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
連理が突然腕を引き、紗藍を立ち上がらせたので、彼女は思わず足を絡ませ転びそうになったが、なんとか体勢を立て直すと、いつになく厳しい顔で連理を睨んだ。
周囲が騒がしいのは事実だが、さっき声を上げた者は奥に加勢を呼びにいってしまい消えていたので、追っ手はまだ、すぐ近くという訳ではなさそうだ。ただいずれにせよ、彼女はそんなことには構うつもりがなかった。
今すぐにでも連理に言っておきたいことがあった。彼女にとってはそれが何より重要だった。
「結麻の竜のことは私は知らない。でも私は結麻を殺すなんてそんなこと、絶対にしない」
「紗藍様は当主でしょう。先ほどご自分で『自覚を持とうとしている』とも仰った。ならばその自覚を確固たるものにする、今回は良い機会なのではありませんか? 部族内に立つであろう波風を、先んじて、あるいは小さいうちに絶っておくのも当主の一つの務めです」
語調を全く乱さずに答えながら、連理は肘を引くとそれを紗藍の方に突き出した。紗藍は自分の頬を掠(かす)っていった彼の手に思わず身をすくめ、直後背後で嫌な音と臭いを感じ取った。
何かが燃えている。草や木や、布ではない。意味をなさない音、いや、声。
彼女は振り返れなかった。伏せた顔を上げられなかった。そこで何が起きているか、見ずとも分かっていた。連理は燃やしたのだ。
それは確かに、自分を狙っていたのかもしれない。連理は自分を守ってくれたのかもしれない。しかし連理は燃やした。
人を。
「これが我々の仕事です。紗藍様」
連理の言葉はあくまで平静だった。まるで人の声ではないかのように。
行きましょうと連理が背を向け、そこに代わるように炎遥が現れる。なにもない宙から身のこなしも軽く降り立った彼は、屋敷の中を動き回りやすい姿を選んだのだろう、人の姿をしていた。その炎遥の気遣うような表情の前で、紗藍はまだ顔を上げられずにいた。
目の前で起きていること、そして自分に与えられた当主という立場。連理の言う「我々」の長としての立場。耳は熱いのに、自分の背中はすうと冷えていく。彼女には、その感覚すら怖かった。
彼女は無言で手を伸ばすと、炎遥の着物の裾を握りしめた。白い腕が背後で崩れ落ちた炎に照らされ、がたがたと震えていた。
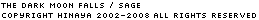 (13)
(13)