xii / Linaria bipartita
風に葉がこすれる音以外何も聞こえない竹林の中で息をひそめているのは、思ったよりも大変なことだった。空を見上げれば月明かりが照らしているが、それでもしゃがんでいる足元は湿り気があるせいか、実際の暗さ以上に妙な重苦しさを感じる。
自覚はないが緊張しているのだろう――結麻はため息をつき、折っていた膝を伸ばして立ち上がると、後ろでほとんど動きもせずにずっと屋敷の方を見ていた翠嵐に声をかけた。
「あんまり根(こん)詰めすぎると疲れない?」
「別に。根詰めてる訳でもないし」
「でも、いつになく真面目に見えるわ」
というより「深刻」かなと結麻は肩をすくめた。いつも(内心はどうであれ)気のない返事ばかり、やる気の片鱗も見えないような彼には珍しいことだ。危険を伴う仕事の相方として本来ならこれは喜ぶべきなのだろうが、彼女にとっては「らしくない」と思わせるだけで、ただ違和感のみ残る。
しかし、それはそれでいいとも思っていた。本来なら、とか、普通なら、とか。そういった他人の基準に合わせる必要などない。結麻は翠嵐の隣に立ち、彼と同じ方向、屋敷の方を眺めた。
「紗藍たちはうまく中に入れたかしら」
そう高い訳ではないものの、塀がぐるりを取り囲んでいる屋敷の中は、結麻たちの位置からははっきり低い位置を視界に捉えることができない。とは言え静かな晩だ。騒ぎが起きれば音は昼間以上によく響く。静かなままであるということは、気付かれずに侵入することができたのだろう。
それに、紗藍には連理がついている。経験豊かな年代とは言い難いものの、それでも結麻たちとは比べ物にならない場数を踏んでいるし、山吹と見せる連携は集落の者にも一目置かれるほどだ。その上今回の屋敷は彼が以前も仕事をした所だという。ならば心配はないはずだ――そう考え、結麻はゆるゆると息を吐いて、屋敷の屋根を目に入れたまま再びしゃがんだ。
「あんまり信用し過ぎるなよ」
「え?」
顔を上げて聞き返した彼女に目を落とし、翠嵐は肩をすくめて返事をした。
「連理」
結麻は眉を顰めた。頭の中を覗かれていたことに対してではない。
「信用しちゃ悪い理由があるの?」
「ある」
「何よ」
翠嵐は答えず、ただため息をついて目を伏せた。結麻が見上げた彼の顔の向こうで、丸い月に薄雲がかかり、そして流れていった。
周囲で小さな音がする。もしかすると雨の後、根が張られていく、そして竹が伸びていく音なのだろうかと思い、結麻はそれに耳をすませてみようとしたが、質問をしたまま返事がないのはどうにも間が保たなかった。半ばやむなく、彼女はもう一度口を開いた。
「翠嵐」
「何だよ」
「何で連理をそんなに嫌うの?」
見上げた結麻に眉を上げた翠嵐は、答えのためにか僅かに口を開きかけ、そしてそこに言葉を乗せる前に屋敷とは逆の方を振り返った。
彼の視線の先を追った結麻の目に、火の爆(は)ぜる音とほぼ同時、視界を覆うように広がる炎が映った。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
連理が口にした事実は紗藍にとっては予想だにしないことで、彼女は思わず言葉を失った。
この屋敷、この家に「当主」など既に存在していない。彼は最初に、そう言ったのだ。
床の高い渡り廊下の下、すぐ傍で聞くには辛うじて差し支えないと言える程度の声だった。
「実際仕事を受けた者しか確かめようのないことですが、前回我々は確実にこの家の当主の命を絶ちました。後を継ぎうる者は傍系もです。ですから今この屋敷にいるのはかつての従者や使用人のみ。いずれはその時の依頼者に、領地もろとも接収されるでしょう」
表情を変えることなく先を続けようとする連理に、紗藍は思わず身を乗り出して続きを制した。彼女が地面についた両膝の下で、砂利がこすれて音を立てた。
「どういうこと? それじゃ、私たちが今回受けた依頼は」
「依頼を受けたのは事実です。ただ依頼者がその、当主がもういないという事実を知らなかったというだけ」
「どうしてそうと伝えないの? それに前回きちんと仕事を成功させたのなら、依頼者だけにでもはっきりさせておかなきゃ、この先仕事の確実性を疑われることになってしまう。第一、私たちが危険を冒してまでこの屋敷に侵入する必要性は」
ない、と言いかける紗藍に、連理は頭(かぶり)を振ってみせた。
「あります。依頼者にはもう我々をここに忍び込ませる必要などないのでしょうが、我々には有益――というより、絶好の機会なのです。私が瀬尾結麻を一人にした理由が分かりますか?」
紗藍は顔色を変え、振り返った。塀の向こうの竹が頭を覗かせているが、ここからでは結麻は見えない。逆もまた然りだろう。その彼女の様子が目に入らないとでも言うかのように、連理は淡々と話を繋いだ。
「今の瀬尾家に大した力があるとは思いません。かと言って捨て置いて、知らぬ間に勢力を盛り返されても面倒なことになるのみ。根を絶っておく方が安全です」
言葉の最後を連理は、念押しするような口調で「紗藍様」と括った。
彼は古くから度会に組する湯木家の跡取りだ。度会家、そしてその当主たる紗藍を半ば主のように仰ぐ彼は、頭を低くし片膝をついて、目線だけ上げると彼女を見た。紗藍は狼狽えたが、少し間を置き首を振った。
「結麻は私にとっては、すごく大事な」
「いいえ、ただの邪魔者です」
彼女の事情は連理にとっては何の意味も持たなかった。正確に言えば「紗藍」の事情などどうでも良かったのだ。それは家の利益に反する。そうであれば優先されるべきは後者だ。
紗藍の言葉の続きを有無を言わせず切り捨てた連理は、すくと立ち上がると山吹を呼んだ。彼はすぐに現れた。紗藍が知る限りでは、結麻と親しかったはずの山吹。少なくとも結麻は彼を信用していたし、またある意味では愛してもいた。
紗藍の目の前で、二人はごく短かな言葉を二つ三つ交わし、そして山吹がいつもの表情のまま頷いて、消えた。彼女が二人の小さな声から聞き取った限り、山吹はこれから火を放ちにゆくのだ。屋敷にではない。この丘の周囲に、結麻を追い込むために。
雨が降った直後の湿り気の多い状態であるとは言っても、人間が火を焚き付けるのとは訳が違う。炎そのものが意思を持って暴れ回るのだ。未遂では終われないことくらい紗藍にも分かった。彼女はごくりと唾を飲み込んだ。当初は屋敷に火を放つ予定だった。しかし。
「これだけの広さが全部焼けてしまえば、どこが火元かなんて……」
「都合が良いでしょう。瀬尾家の当主は自らの無経験を顧みず、私の指示に従わずに功を焦って屋敷に入った。その結果返り討ちに合い、任務を果たした我々はやむなく彼女を屋敷と共に灰に。実際は事情を確かめるため、あるいは火を逃れるために屋敷に来たのであっても、事後的に生存者がそのような筋書きをつけるのは簡単です」
「結麻に見取り図を見せたがらなかったのはそのため? 中に入って、この家にはもう当主なんていないことに気付かれると面倒だから」
激しく咎める紗藍の視線を軽くいなし、連理はすいと目を外に向け、呟くように答えた。
「そこは気付かれようと気付かれまいとどうでもいい。見取り図を覚えられたくなかったのは、我々の身の安全を考慮してのことです」
「結麻が私たちに矛先を向けてくる? そんなはずないよ、だって」
「彼女自体は大した問題ではありません。ただ彼女がその情報を得た場合、確実に伝える相手が。彼女にはそういう宛てがひとつしかない」
意味を掴み損ねて眉間に皺を寄せた紗藍に、真直ぐ向けた目を連理はすぐに伏せた。
「彼女の竜。あれは己の意思で動く。それは最早我々の知る竜とは違います」
そこでひとつ息をつき、連理は立ち上がった。屋敷の者が二人に気付いて加勢を呼ぶ声が聞こえたが、彼はそれを全く気にかける様子もなく、言い放った。
「あれは、おぞましい」
屋敷の東で、火の手が上がった。
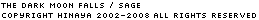 (12)
(12)