xi / Anemone coronaria
結麻が紗藍、連理と共に目的地に着いたのは、それから三日後の晩。日がとっぷりと暮れてしまった頃だった。
連理の話した通り、その屋敷は小高い丘の上にあった。周囲は厚い壁のように竹林で取り囲まれているため、丘を登りきるまでは屋敷はただ屋根の先が見えるだけの状態だ。
その竹の隙間に隠れるように屋敷を目指す三人の足元、地面は濡れてしっとりしていた。この周辺はついさっきまでは雨雲に覆われ、霧雨が降っていたのだが、今はどうやら上がっているらしい。「どうやら」と言うのは雨粒を集めた葉から相変わらず雫が落ちてくるからで、ちょうどつむじにその雫を受けた結麻は、顔を上げると頭を掻いた。
葉のさざめく隙間から見える空に、雨雲はもうほとんど残っていない。煙る夜気の先に朧(おぼろ)に月が見えている。それでも辺りは意外に明るい。足元に自分の影ができていた。
きだはしと同じく海を渡らねば来ることのできないここへの道中、三人は段取りをもう一度確かめてあった。その場に翠嵐は当然いなかったし、また炎遥も山吹もいなかった。厳密に言えば「いる」のだが、姿は見えなかった。きだはしへ向かった時の翠嵐のように、彼らは主の中で眠ることができる。
この集落は「集落」と呼ぶのが気がひけるほど大きく、規模的には町と言って全く問題がない。海岸はほとんどが整備され、他集落との交易船が容易に着けるようにしてあった。ただ結麻たちはそんな所から堂々と上陸する訳にはいかないので、今は使われておらず荒れ放題の桟橋跡を利用したのだが。
そうして入った集落の端から遠目に見える盛り上がった黒い影が、屋敷のある丘だった。彼らは人目を忍びつつ、そのふもとまでやってきて竹林に足を踏み入れたのだ。
この立地――竹に周囲を囲まれている、屋敷の立地――は地竜である翠嵐、そして彼を伴った結麻には絶好の場所だ。外部からの侵入者が、地中に網のように張り巡らされた竹の根に体重をかけようものなら、それはすぐさま結麻に伝わる。その場合は彼女は翠嵐と共に邪魔者の排除に向かう。そうして二人が外側を固めている間に紗藍と連理とが屋敷に侵入し、当主の命を取った後、あるいは取ると同時に屋敷に火を放つ。その火の手を合図に結麻たちも離脱し、上陸した場所で合流、この集落を後にする。簡単に言えばそういう計画だった。
連理がこの役目を自分にあてがったのは正解だ、と結麻は思った。実戦経験のない彼女は先ほどから練習とばかりに周囲に気を配っているのだが、屋敷を挟んだ向こう側でウサギが一跳ねしたこともはっきりと分かった。見える訳でも聞こえる訳でもない。自分の鳩尾あたりにそれを感じ取り教える器官が、頭とは別に存在しているようだ。
これが自分の、いや、翠嵐の能力なのだと彼女は考え、仮にそれがなくなったらとも考えようとして、やめた。意味のないことだ。なくなるはずがない。
あるいは、そう思っていたかった。
「結麻」
「え、あ、うん」
大丈夫? と眉を顰める紗藍に肩をすくめてみせると、結麻はそこから見える屋敷の塀に目を細めた。
白壁に遮られた先に、茂った背の高い草。その向こう、渡り廊下の奥では格子の間から淡い橙の光が漏れている。度会の屋敷ですら比べ物にならない、これでもかとばかりに大きな屋敷だ。連理が紗藍と二言三言の言葉を交わし、紗藍は頷いてからもう一度結麻を見た。ここから当初の計画の通り、紗藍と連理とは先へ、結麻は待機と二手に別れるのだ。
「それじゃ、私たち行ってくるね。結麻はしばらく一人になっちゃうけど……」
「ん。任せて」
二人の様子を特に何の表情を見せるでもなく見守っている連理を後ろにして心配げな顔を見せた紗藍に、結麻は、大丈夫だってと苦笑を返した。二人と別れた所で彼女は一人になる訳ではない。彼女は自分の右斜め前、誰もいない空間に向かって翠嵐を呼び、さくりと足のつく音を立てて背後に現れた彼に告げた。
「さ、初仕事よ」
翠嵐はいつも通りの気のない返事をし、そして紗藍の後ろでこちらを見ていた連理に僅かに目を細めた。嫌悪も好意も媚びも軽蔑もない。ただ、すいと細めただけだ。竜の細いそれとは違う、まるい瞳孔の人間の目を。
連理がその目を睨み返したのに、結麻は気付かなかった。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
拍子抜けするほどやすやすと塀を越えて屋敷に侵入した紗藍と連理は、人目につかない場所を選びながら目的の場所に向かった。
複雑とは言えないまでも、それなりに凝った作りの屋敷だ。渡り廊下の中には、地面から柱で支えた少し高い位置を通るものも多く、人が通る足音を頭の上で聞くこともできるであろうその真下を通りながら、紗藍は必死に屋敷の見取り図を思い起こした。
結麻には見取り図をあまり見せない方が良いと連理は言った。結麻もそれで引き下がったようだったが、紗藍はその時感じた違和感を未だ引きずっている。確かに何もかもが予定通りに進むのなら、結麻は屋敷の間取りを分かっている必要はないだろう。しかし必要がないのと「知ってはいけない」のとは別だ。連理の態度は強硬に過ぎると感じていた。
そしてそれに何か理由があるなら――そう考え、紗藍は目を伏せた。足元には黒い土、背の低い草がまばらに生えている。暗い中ではあるが、見渡してみればあまり手入れが行き届いているとは言い辛い庭だ。これだけの大きな屋敷を抱える家にそれはそぐわない気がして紗藍は首を傾げた。自分の家はこれほど大きくはないが、手入れはしっかり行き届いている。
例えばこの家が今は落ち目で屋敷は過去の栄光だというのであれば、こういうこともあるだろう。しかしそれなら相手は、自分たちに高い報酬を約束してまで依頼をする必要もないはずだ。少し先で彼女の来るのを待っていた連理に追いつくと、そこで彼女は彼に質問を投げかけた。
「連理」
「はい」
「ここの人って、どういう人なの?」
連理は少し考えてから、僅かに首を振った。
「この辺り一帯を支配する、言うなれば領主のようなものです。周囲の集落を次々と傘下に繰り入れている、かなりのやり手でした。それ以上のことを知る必要は、ありません」
彼はそう答え、またすぐ前を向こうとしたので、紗藍は眉を顰めて彼の裾を掴み、自分の方を向かせた。「でした」に彼女はひっかかりを覚えずにいられなかった。かと言ってそれが意味するのが何なのか、紗藍には掴めなかったのだ。
「私たちに依頼をしてきたのは確か『対抗勢力』だったよね?」
彼女の質問に連理は一度目を伏せて、周りに人のいないのを今一度確認してから口を開いた。
「紗藍様。今回我々に依頼をしてきたのは正確には、対抗『し得るほどの』勢力ではなく、先ほど言いました『周囲の集落』になりかけているうちの一つです……が」
が? と先を促した紗藍に、連理はため息をついて続けた。
「紗藍様は度会家の当主としての自覚はおありですか?」
「え?」
「おありですか」
否と答えるのを許さないような尋ね方に気圧(けお)されながらも、紗藍は肩をすくめて返事をした。
「持とうとは思ってる。あるかは分からないけど」
「結構。では」
屋敷を取り囲む竹の梢が、丘を駆け上る風にざわとさざめいた。
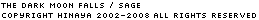 (11)
(11)