xx / Fagopyrum esculentum
早稲の急逝に、集落はひとときの混乱に陥った。それでも「大混乱」とまで行かなかったのは、ひとえに紗藍の手腕によるもの――少なくとも周囲の者はそう判断した――で、葬儀の時も、その後の仕事のとりまとめも、十八歳の少女とは思えないほどの采配を振るった紗藍に対する集落民の信頼は一気に増し、彼女はあっと言う間に名実ともに度会家の当主となった。そこに傍系が入り込む隙間はなかった。
紗藍は始めようとしている。
彼女が「自分はこの集落を変えようと思う」とそう言った、計画を。
彼女がそこまでの対処ができたのは、前もって準備をしていたからなのだろう。ただ、そう考えていたのは結麻だけで、それは何も知らない人々からすれば、紗藍の当主としての資質に大いに期待を寄せる材料となっただけだった。
紗藍はそこまで考えて、計画に着手したのだろうか。早稲の死後、初めての任務を承った帰り道、結麻は立ち止まってため息をついた。そこにいると、未だに山吹が垣根の隙間から顔を覗かせそうな気がして期待してしまうのだが、それはあり得ないことだと気がつき、また虚しくなる。
この一年で、何もかもが変わってしまった。
紗藍は自分が思っていたような少女ではなかったし、もしかすると自分もまた、変わってしまったのかもしれない。
向こうから、四、五人の子供に足元を取り囲まれて鬱陶しそうな顔をしながら歩いてくる人影を見つけ、結麻は肩をすくめた。向こうもそれに気付いたようで、これをどうにかしてくれとばかりに彼は子供を指し示す。結麻は一度顔を伏せると笑顔を作ってから顔を上げ、そちらに走っていった。
カラ元気でも、元気には違いない。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
二人で囲む、というより「向かい合う」食卓。それが当たり前になったのも、この一年のことだ。
「なんで子供に囲まれてたの?」
「この虫の名前は何だ、雲はどうやってできるんだ、どうして風が吹くんだ、この集落の外はどうなっているんだ、その他諸々質問攻め」
「物知り認定されたのね」
「光栄過ぎて涙が出るね」
勘弁してくれと呟いて箸を伸ばす翠嵐の方へ器を押して、結麻は自分の箸を置くとため息をついた。
翠嵐と一緒に暮らすようになって、仕事ができるようになって、そしてその仕事の中で連理と山吹を失い――そして早稲が死んで、紗藍は手の届かない人になってしまった。
音にならないため息を漏らして食卓に両肘をつき、組んだ手に額を置いて結麻は目を閉じる。前で食器を重ねる音がし、彼女はちらりと目線だけを上げた。
翠嵐の手が見える。決して逞しくはないけれど、それがそこにあることに今までどれほど安心したことか。この一年、彼だけは変わらないのだ。それどころかもし自分が死んでしまっても、その時自分が契約を切り、彼を自由にしさえすれば、人間のような寿命のない彼は永遠に在り続ける――今のままの姿で。
自分が死んでも、翠嵐は変わらない。
別の主にも、彼はまたこうして安心を与えるのかもしれない。
そこまで考えて、結麻は顔を上げた。
「翠嵐は、変わらないのね」
「あ? 唐突に何だよ」
立ち上がりかけていた翠嵐は、肩をすくめて椅子にかけ直した。
「私の周りは、みんな変わってしまったわ。連理と山吹はいなくなったし、紗藍はもう『友達』なんて呼べない人になってしまった。今まで私を遠巻きにしていた人たちはそれをやめたけど……でも、変わってしまった」
「一年あればな、色々変わるだろ」
気のない返事をする翠嵐に、結麻は眉を寄せて頬杖をついた。
「翠嵐が私の話を真面目に聞かないのは、変わってないわ」
「俺はいつも通りだ」
「私がいなくなっても、そうなのよね」
いきなり何を言い出すのだという顔で、翠嵐は結麻をまじまじと見つめた。結麻は僅かに後ろに引いて、たどたどしい口調で言葉を選ぶ。
「だって、そうでしょ? 翠嵐は私みたいな人間と違って、もうずっと長く生きてきてるんだし、これからも……」
「前半は合ってるが、後半はどうだろうな」
「どういうことよ」
結麻が続きを待つ前で、翠嵐は座面に足を上げて欠伸をし、そのまま目を閉じてしまった。結麻が繰り返し続きを促すと、彼は「眠い」と呟き立ち上がった。
「言うべきことをはぐらかすのも変わってないわ」
結麻はため息をつき、部屋の奥に向かう彼の背中を追う。
ただ、それと必ず一緒に、もうひとつ変わっていないことがあるのも、彼女はよく知っていた。そういう時、彼は「口に出さない」だけなのだ。
――山吹を不幸せな奴だと思う。その気がないのに主と心中することになったから。しかし自分がそうなったら、それはむしろ幸せなことだとさえ思う。山吹が連理に持っていた想いと自分が結麻に持つそれとは、全く異なるからだ。
言葉にするなら恐らくそういう文章になるのだろう。ただ形を捉えようと手を伸ばせば霧散してしまいそうだったので、結麻はそれを確かめることはしなかった。それでもとても曖昧で、繊細で、それでいて温かな風に包まれた気がして、結麻はゆるゆると笑った。
「ねえ翠嵐」
立ち上がりながらそう言った結麻を振り返り、彼は眉を上げた。
「翠嵐みたいなのって、人間どうしだったら絶対誤解されると思うのよね」
「人間どうしじゃないから別にいいだろ」
「でも、人間は聞きたいのよ」
「お前も聞きたい訳」
観念した、とでも言いたげに翠嵐は大きなため息をついて手招きをした。結麻はそれに応え、彼のすぐ目の前で顔を上げると真直ぐ目を見る。言えるものなら言ってみろとでも言わんばかりの、挑戦的な視線だ。
「なんか、前もこういうことあったな」
翠嵐は苦笑を漏らし、そうだった? と首を傾げた結麻も思い当たったようで苦笑を返した。
「呼び出した時もこんなだったわ」
「なんとまあ色気もなく小憎らしい小娘かと思ってがっかりしたもんだよ」
視線を下ろし、なんて奴、と呟いた結麻に、で? と翠嵐は肩をすくめた。
「今はどうか、本当に聞きたい訳」
「変わってないのなら言わなくていいわ」
翠嵐は降参とばかりに両手を上げ、ちらと目を上げた結麻の耳を摘(つま)んで引っ張ると、これ以上ないほど近く顔を突き合わせた。
「分かれよ、小娘」
「言いにくいことを言わせるな」。それで結麻には十分だった。
それでも彼女はぎゅうと音がしそうなくらいに強く彼を抱きしめ、笑いながら「言いなさいよ」と繰り返した――それでも、涙がこぼれた。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
小さな集落で起きた、ひとりの人間の少女と、ひとつの人ならざるものの話。
それから数百年。集落のあった場所には生の気配はなく、ただ家の礎であった石だけが長年の風雨に摩耗し、刈るもののない草が砂まじりの風にさわさわと揺れている。
prev
|
...will go on to "colours"
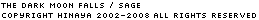 (20)
(20)