i / Linum usitatissimum
一日とかからずぐるりを歩いてしまえそうな小さなその島にはひとつ集落があるだけで、そう人数も多くない一部族が住み始めて数百年を数える。
砂の踏み固められた黄色い道沿いにぽつりぽつりと目に入る家屋は、どこも似たような外見をしている。石を積んで作った平屋を密度の低い生け垣が取り囲む、飾り気はあまりないがしっかりした造りで、余程急激な家勢の衰えでもない限りは家族が代々ひとつの家に住み続け、移動もない。
正午を間近にからりと晴れた空の下、人の背丈ほどの竜が一頭、乾いた色の生け垣の隙間から頭を出し、外の様子を窺(うかが)った。
彼――あるいは彼女だろうか。その竜は視線の先に人影を認めると、ひょいと首を引っ込めて一度中に入り、少し先に設けられた木戸を器用に鼻で開けて道に出た。鱗のようなごつごつとした皮膚に包まれた脚は、心もとないほど細い手に比べると不釣り合いなくらい発達している。その足が砂地に三つ又のような足跡を数個つけた先で立ち止まった竜は、人影が背に垂らした薄茶色の髪を揺らして手を上げたのに返事をするように、太く長い尾をゆったりと振った。
「おはよう。山吹(やまぶき)」
竜に手の届くところまで来た少女は、物怖じすることなく自分ほどの背丈(あるいは彼女の方が低いかもしれない)の竜の鼻面を撫で、顎の下をくすぐった。ぐるる、と喉の鳴る音がする。しかし彼女にはそれが言葉であることが分かる。何を言っているのかも。そしてそれはこの、皆が紫色の瞳を持っている集落では、彼女だけに特異な能力ではない。
<誕生日おめでとう、結麻(ゆま)>
その竜、山吹はそう言ったのだ。それに満面の笑みを浮かべると、結麻は山吹から離れた。
「今日、契約竜を呼び出すの」
<もうそんなになるのかな>
「あれから十一年だもの。私、今年で十七よ」
山吹は瞳孔が線のようになった灰色の目を細めた。
<使いやすいのが呼べるといいね>
結麻は肩をすくめ、実はね、と頬を掻いた。
「こないだ納屋から出てきた『扉』を使おうと思ってるの」
<あの、珍しい形の?>
「そう。変なのが出てきそうだからやめろって言われたんだけど、そう言われると余計呼んでみたくなるでしょう?」
苦笑を漏らした(もっとも竜にそういった表情があればの話だが)山吹は、尾の先に小さな橙(だいだい)色の火を灯し、それを高く掲げながら頭を下げた。
<幸運を>
「うん、ありがと」
結麻は先ほどよりは少し落とした笑顔でそう返し、山吹が木戸をくぐって中に入ってしまうのを確認してから、その場を後にした。
この集落に限らず、紫の目をした人間はほぼ例外なく、竜と通じる能力を持っていると言われている。人間には自由に操ることのできない力をそれぞれに帯びた竜を呼び出し、それと契約を結ぶことで、彼らはその能力を我がものとして使うことができるのだ。
そうして契約を結んだ竜は、主との契約を解除するまで――そのほとんどが「主が死ぬまで」、その傍に付き従うのが通例だった。山吹の場合もそうだ。契約を結んだ後は、主と同じ場所に住んでも邪魔にならない大きさに姿を変え、必要とあらば人の姿を纏(まと)って、主の言うがままに「仕事」の手伝いをする。それがこの集落、そしてこの近辺に散在する別の島の集落――紫の目を持つ者たちの集落での常識だった。
竜の側がその立場に甘んじているのは、彼らがもともと形ある存在ではないことに起因する。そうして契約を結んでいなければ、彼らは実体を持って存在することができないのだ。そうした状態を観念できない人間からは想像もつかないものだが、それは彼らにとってはこの上ない魅力であるらしい。少なくとも山吹は、結麻にそう語った。
しかしそれが事実だとしても、結麻にとって現況はあまり納得のいくものではなかった。仕事の道具としてだけ彼らを利用するのは彼女にはいい気分ではなかった。彼らとて感情のある生き物だし、山吹のように目をかけてくれる保護者のようなものもいるのだ。彼女には竜、触れれば冷たく固い皮膚を持つ竜の方が、人間よりよほど暖かなものに感じられていた。
彼女は部族の長老らが待つ場に向かいながら、自分が呼び出した竜にはそういった制約を課すことはやめよう、と決めた。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
辿り着いたのは集落の外れ、小高い丘を覆う林の頂上部に設けられた小さな円形の広場のような場所で、そこだけは地面が土でも砂でもなく、石に覆われていた。
中央に敷かれた「扉」に結麻は目を細めた。彼女が昨日、訪ねて来た長老の使いに渡したものだ。くるくると筒状に巻いた状態で長い間納屋に放置されていたので、見つけた時に試しに広げてみると、端が反り返ってしまいどうしようもなかった。扉と呼ばれるのは機能のためで、実際は紙のような形状をしている。
しかし今、風が梢を揺らしていっても、その薄くて軽そうな「扉」は全くめくれたり飛んでいったりしそうな様子をみせず、そこで厳かに使われるのを――「開かれるのを」待っているようだった。その周りを、見下ろしながらゆっくりと回った結麻は、一度深呼吸をしてから数歩後ろに下がった。
「扉」は形なき世界と現世とを繋ぐ道具だ。代々口伝される言葉と一体となって、その世界に住まう一定の条件を満たした竜を呼び出すもの。「扉」に記された図形と、呼び出されるべき竜が備えている能力の種類や強さにはある程度関連があり、条件は図形を見れば大抵把握できたので、契約竜を呼び出すに当たっては、自分に合った条件のものを得るために「扉」を選ぶ者が多かった。
しかし結麻の選んだものは、これまでほとんど例のなかった形を備えていた。幾何学的な線の引かれたその図形は左右は対称ではないし、基礎となるべき円も楕円で何やら収まりが悪い。その上その楕円の中では、記号というより何か文字に近い、ひとつとして同じもののない小さな印の羅列が、解放を求めひしめきのたうっていた。
いくつかの特徴は、それの呼び出す竜が格の高いものであることを示していた。三双の翼を持ち、強大な力を備えたもの。しかしそれは主たる人間にとっては付き合い方が難しく、時には竜の側から愛想を尽かして逃げてしまうことがあるのも確かで、言うなれば「上級者向け」だった。
だから長老は、初めて契約を結ぶ結麻にもっと簡単に扱えるものを呼び出すように勧めたのだが、彼女は聞かなかった。その理由を知らなかった訳ではないが、それが主な理由でないことも彼女は知っていたからだ。
そして今日。長老は、準備体操をするように首を曲げた結麻の後ろから、最後の機会とでも言いたげな顔で彼女に尋ねた。
「何が出てきても知らんよ。本当にいいのかね」
「紗藍(しゃらん)の時は、ありったけ強いのを選んだって聞いたんだけど? あの子と私は何が違うの?」
渋い顔で口を噤(つぐ)んでしまった長老と、にわかに険しくなった周囲の数人の男の様子に肩をすくめ、結麻はもう一度深呼吸をすると一歩踏み出した。
結麻が「仕事」の中で命を落とした両親に代わり、祖父母に育てられるようになったのは十一年前だ。その祖父母も数年前に他界し、彼女はこれまでを、山吹をはじめとする集落の親切な竜の助けを借り、ほとんど一人で生活してきた。
瀬尾(せのお)。結麻の姓であり、この集落の中では今一番の権勢を誇る度会(わたらい)家とかつては肩を並べていた家の名だ。最盛期には集落の誰もがいずれかの派閥に属し、仕事を奪い合っていたほどだった。
しかし当主とその妻とが幼い娘を遺して没したのを機に瀬尾から度会へ移ったものが相当の割合いたし、何しろ小さな集落だ。大勢はすぐに変わり、瀬尾の新当主となった少女は半ば孤立した形となって、あまり恵まれた暮らしを送って来なかった。彼女はその時竜と契約のできる年齢にはほど遠く、当主の実力がそのまま求心力となるこの部族では無力な存在でしかなかったからだ。
度会と張り合うつもりは結麻には毛頭なかったし、つい数ヶ月前契約を済ませて度会家新当主の座に収まった同い年の少女、紗藍を目の敵にするつもりもまったくなかった。彼女はこの狭い集落の中では、大っぴらにはし辛いものの、無二の親友と言って良かった。それは今でも変わらない。
しかし周囲の大人に二人の個人的な友情は関係がない。今やほとんどが度会についていた集落の者たちは、旧勢力たる瀬尾の氏を背負っている結麻を冷遇した。紗藍にできるだけ強力な竜と契約を結ばせようと集落中の「扉」を探しまわっていた時の騒がしさといったらなかったのに、結麻が契約竜を呼び出す今日のこの落差も、そのひとつだった。
これが今の、いや、「今までの」結麻の立場だ。
彼女はこれから自分の竜を呼び出し、それと契約をする。そうして仕事につくことが許されるようになれば、割り振られた仕事をこなして一人前と認められる日もあるはずだ。
家の再興などどうでもよかったが、周囲が彼女を認めざるを得なくなる、その線に立てることが何よりもうれしかった。
たとえその「仕事」、自分の部族が生業としてきた仕事が、日の当たる世界では忌み嫌われるものだったとしても。
結麻は「扉」の前で両手を合わせ、目を閉じると祖父に教わった言葉を紡いだ。
背中に垂れた彼女の髪を遊ばせていた風が止み、扉の上の文字がぞわと蠢いた――ように、見えた。
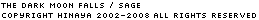 (1)
(1)